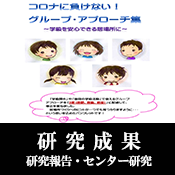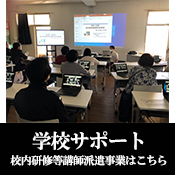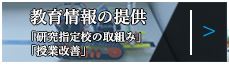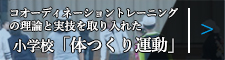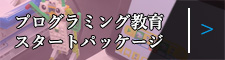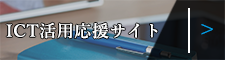お知らせ
県総合学校教育センターでは、職員の働きやすい環境づくりの一環として、軽装(ノーネクタイ、上着なし等)で対応させていただいております。 ※A-biz…Aomori(青森の)All-season(1年を通じて)Airy (軽快な・風通しの良い)
令和6年度研修講座の申込みを受け付けております。「研修講座案内」をご覧になり、受講を希望する講座の「講座概要」にある「受講・聴講申込みURL」をクリックしてお申し込みください。
本日より当センターWebページを更新しました。
トップページをスリム化したため、これまでの場所とは違うものも一部ありますので、御利用の際は注意ください。
目的のものが見つからない場合は、右上のサイトマップを御活用ください。
{{item.Topic.display_publish_start}}
{{item.Topic.display_summary}}
新着情報
講座番号D17「特別支援教育新担当教員研修講座[知的、肢体、病弱、通級コース](前期)(後期)」について、再度、ご案内いたします。
期日:5月21日(火)・11月22日(金)
※詳しくは、講座概要をご覧ください。
受講申込み締切は4月26日(金)までとなっております。
3月8日(金)にセンター広報誌「センターだより」第75号を発行いたしました。
こちらからご覧ください。
2年目研究員の研究論文がWebアップされました。こちらからご覧いただければと思います。
{{item.Topic.display_publish_start}}