
6月18日(火)、19日(水)に標記講座を開催しました。12名の先生方が参加し、NetCommons3の操作方法について、実際にサンプルサイトを最初から作成しながら学習しました。受講された先生方は、CMSを活用したWebページ運営について具体的なイメージを持つことができた様子でした。
【講座の内容】
18日 WebページとCMS 19日 ルーム管理
設定・管理画面 SFTPによるファイル転送
基本ページの作成 総合演習
プラグインの利用


【受講者の感想】
・ページ作成の仕方や、合格発表のアップの仕方等、大変実践的に学ぶことができ、大変参考になりました。
・今までホームページの作成は公私ともにやったことがありませんでしたので、今回の講座でその仕組みを大体知ることができて目的は達成されたと思います。
・NetCommons2から3になり、操作方法がわからない部分があったが、今回の講座でわからない部分が解消されたので良かった。
6月18、19日に中学校理科実験講座が開催されました。受講された先生方は12名となり、活気あふれた講座となりました。地区によっては、中体連の振替休日にも関わらず、講座に参加された先生方もいました。日程は以下の通りです。
6月18日(火)午前:講義「理科授業改善の視点」
午後:講義・実験「授業で使える観察・実験の工夫」(3学年1分野の内容)
6月19日(水)午前:講義・実験「授業で使える観察・実験の工夫」(1学年1分野の内容)
午後:講義・実験「授業で使える観察・実験の工夫」(2学年2分野の内容)
【講座の様子】
・ダニエル電池は市販の実験装置よりも少ない薬品でできたり、個別実験にすることもできたり、いろいろなアプローチを試みることができることが分かりました。ウラニン、酢酸ダーリア、メチレンブルーなど知らなかった色素や試薬の特徴を知り、今後の実験観察の幅を広げることができました。音などもちょっとした工夫ではっきりと結果が変化することが分かり、生徒たちの興味関心を高められると感じました。
・複数の実験方法を体験したことで、その実験のよさや改善したい部分が見えてきました。実際に授業で行うときには、実験のよい部分を組み合わせたり、改善したりしながら、生徒にとって分かりやすいものにしていきたいと思います。
・全国学力学習状況調査や県学習状況調査の結果を確認し、様々な角度で考えることができました。また、実験も大変勉強になりました。
・全国学力学習状況調査等各調査の結果の見方について、学ぶことができました。また、いろいろな実験の課題や留意点についても考えることができ、今回の受講の目的を達成することができたのではないかと思います。
6月4日(火)~5日(水)の2日間、標記講座を開催しました。
1日目は、文部科学省 教科調査官の小林恭代氏を講師に、図画工作科の講義と造形遊びの演習を行いました。2日目は、音楽科の講義と音楽づくりの演習及び造形と音楽のコラボレーションの演習を行いました。
【講座内容】
1日目:講義「図画工作科における指導と評価の一体化」
演習「「造形的な見方・考え方」を働かせて資質・能力を育成する造形遊び」
2日目:講義・演習「「音楽的な見方・考え方」を働かせて資質・能力を育成する表現活動」
演習「造形と音楽のコラボレーション」
協議「これからの図工と音楽の授業づくり」
【講座の様子】
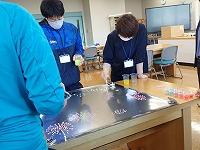

【受講者の感想】
・造形遊びの意義や評価の仕方を学ぶことができ、大変勉強になりました。特に、午後の演習では実際に子供の視点で活動してみて、様々な「見方・考え方」に触れ、色を組み合わせる経験、素材のよさを見つける経験等、様々な経験をすることが子どもたちの感性を豊かにすることができると感じました。
・題材毎に、「音色」「リズム」などの音楽を特徴づける要素の中で、子どもたちに何に気付かせたいかという視点をもって授業に臨むことが大事だと分かりました。学年に応じて絞って指導したり、見方・考え方を意識できている児童を取り上げて褒め、学習をつなげていくことも勉強になりました。
6月11日(火)標記講座を開催しました。14名の先生方が受講されました。
午前は、ICTを効果的に活用した授業づくりの考え方や例について、中学年から高学年へつないでいく視点でお話をさせていただきました。また、「ICTを活用した授業実践」では、弘前市立東小学校の齋藤泉先生に、話すこと[発表]でシンキングツールを活用した貴重な実践を紹介していただきました。動画の中で児童が楽しみながら生き生きと英語で発表する様子が印象的でした。発表後にたくさんの先生方から御質問をいただき、充実した時間となりました。
午後は、東京学芸大学の粕谷恭子教授に講義をしていただきました。「言葉に意味をもたせる」「意味が音を出す」という粕谷教授のお話を通して、言語活動を通してどのように指導すべきかの具体を教えていただきました。受講者の先生方が指導の仕方を体験する場面もあり、あっという間の3時間となりました。
【講座の内容】
・ICTを活用した外国語・外国語活動の授業づくり
青森県総合学校教育センター 指導主事 長谷川 紘一
・ICTを活用した授業実践
弘前市立東小学校 教諭 齋藤 泉
・外国語・外国語活動の指導の在り方
東京学芸大学 教授 粕谷 恭子

【受講者からの感想】
・決まった英単語やフレーズの暗記ではなく、意味を音声化した言葉としての英語を話す子供を育てることが重要だと感じました。文字に頼らずに 肉声で展開する授業を明日から心がけていきます。
・スリーヒントクイズや、外国語を日常的に使うことなど、取り入れていけそうなことを少しずつやってみたいです。
・実際に試してみたい技術が満載でした。
・とても参考になりました。「まずは耳から学ぶ」ことを意識して働きかけることを実践していきたいです。また、発表者の先生の実践から、生き生きと学ぶ子どもたちの姿が見られて勉強になりました。
・粕谷先生の講義の、子どもたちに意味のある音声を届けさせなければならない、という言葉が心に刺さりました。それなりに英語を伝えるのではなく、担任だからこそ話せる英語を伝えたり、構造を意識した英語を伝えたりすることが大切であると学びました。
・小学校外国語活動についての研修に初めて参加したので、なるほど、と思うものばかりでした。今後、小学生への指導に生かしていきたいと思ったし、中学生にも応用できると感じました。
・今後の児童の指導と支援の参考にし、実践したいという思いが高まりました。
・どうやったらもっと子供たちが主体的に活発に活動に取り組むことができるのかずっと悩んでいましたが、今回の講座の中で子供たちが耳で英語に慣れることから徐々に文字に移行していく学習方法に触れ、是非これから実践してみたいと思いました。
6月11日(火),12日(水)の2日間,標記講座を開催し,6名の受講者が参加されました。
この講座は,観察,実験や演習を通して,理科を指導する小学校教員としての指導力の向上と授業改善への意欲を高めることをねらいとして開催しました。
理科の授業改善についての講義,観察,実験の工夫等幅広い内容を取り上げ,理科を指導する教員としての実践力向上を図る内容としました。
日程と内容は,以下のとおりです。
【1日目】午前:講義「理科の授業改善の視点」
午後:講義・実験「観察,実験の工夫~A物質・エネルギー~」
【2日目】午前:講義・実験「観察,実験の工夫~B生命・地球~」
午後:講義・実験「問題解決の力を育む観察,実験」
【受講者の感想】
・「理科の授業をやってみたい」「もう一度、理科を学び直したい」「理科ってやっぱり面白い」といった、たくさんの学びや気付きがありました。子供たちを主体的にするために、まずは、教師が主体的に教材研究や授業準備をすることの大切さを感じました。
・物理、化学、生物、地学の各分野の専門的な知識を生かした実験がとても楽しかったです。教科書にはない知識や身近なものを使った再現方法を知っていると子供をより引き付けることができると感じました。2日間の講義を受けて、理科はやはり実験等を通した実感を伴った理解がとても大切だと改めて感じました。
・思考・判断・表現の力を伸ばすために、日々の授業から「分析・解釈」「構想」「検討・改善」を意識していきたいです。自分でもやってみたいと思える実験がたくさんあったので、挑戦していきたいです。アットホームな感じで受講できたので、気楽に参加できました。「理科って楽しい!」と思えた2日間でした。
・実験がおもしろいのではなく、理科がおもしろいと感じるためには、観察、実験や授業の工夫が不可欠だなと感じました。今回、様々な分野を子供側として体験したことで、子供の思考を実感を伴って知ることができました。授業改善への意欲はとても高まりました。