
11月20日(水)に、桐蔭横浜大学 准教授 清水由先生を講師にお迎えし、C39 豊かなスポーツライフを実現する保健体育授業研修講座を開催しました。清水先生には、体育におけるユニバーサルデザインの基本的な考え方を踏まえた授業づくりについて、講義及び演習をしていただきました。
【研修内容】
講義「体育授業における課題と工夫」
講義、講義・演習「ユニバーサルデザインの考え方を生かした体育の授業づくり」
講師 桐蔭横浜大学 准教授 清水 由 先生
【講座の様子】


【受講者からの感想】
・授業のUD化を図るにあたって、「つまずき」から授業をデザインするということが特に勉強になりました。UDについての研修は受けたことがありましたが、体育の授業に特化した研修は初めてでした。UD体育のしかけについてや、UD化を阻害している原因についても知ることができ、このことを普段の授業にも活かしていきたいです。また、午後の演習では、校種や地域の違う先生方の授業のアイディアを共有し、清水先生に解説していただき学ぶことができとても貴重な時間になりました。ありがとうございました。
・わかりやすい説明で、すっと頭に入ってきた。一番わかりやすかったことは、難しい局面を取り除いてあげるということがUDの仕掛けになるということ。我々体育教員は日々色々考えて授業を行なっていて、それがUDであることも認識できた。それを改めてみんなで共有することで学びになった。
・すべての生徒に分かりやすく、できるを感じさせる授業をするために、今まで以上に授業を細分化して考えていく必要があると感じた。習得したい技の焦点を絞り、視覚化したり不安要素を取り除いたりすることで、運動嫌いの生徒でも体育に取り組む意欲に繋がると思う。体育を嫌いなまま高校卒業とならないように、日頃の授業改善を図っていきたい。
11月18日(月)、19日(火)の2日間、標記講座を開催しました。データベースの演習やプログラミングによるデータの活用と分析などについて学びました。
【講座の内容】
・情報科の指導と評価について
・データベースとSQL
・表計算ソフトによるデータの活用と分析
・プログラミングによるデータの活用と分析
【講座の様子】
【受講者の感想】
・データベースの実習、テキストマイニング、データ分析などの課題について、無理なく授業に展開できそうな感じでしたので今後実施したいと思います。すでに終えた単元については、来年度に活かせるように教材の準備をしていきます。特にデータ分析については、よい事例を教えていただきました。
・情報の分野では教員の専門性が重要となり、新しい技術や教育方法に関する研修を定期的に行い、自身が最新の情報を学び続ける意識を持ち続けていきたいと強く思いました。講座を通して得られた豊富なツールやアイディアを授業の実践に生かしていきたいと思います。ありがとうございました。
11月12日(火)、13日(水)の二日間、標記講座を開催しました。新学習指導要領の内容や観点別学習状況の評価の方法、課題研究等で活用するための制御方法などについて学びました。
【講座の内容】
・学習指導要領 教科「工業」について
・3Dプリンターの活用
・シーケンス制御
【講座の様子】


【受講者の感想】
・評価についての考え方がよくわかりました。生徒の評価の時期でもあるので、学んだ考え方を反映させて、少しでも適切な評価ができるようにしていきたいと思いました。また、演習では、今まで触れたことが無い3Dプリンタとシーケンス制御ということで、実習でもすぐ実践できるような内容になっていたので、テーマになったときに生徒へ指導できるように、自学を続けていきたいと思います。とくに3Dプリンタはちょっと難しいと思ったので、これに関して詳しくやる研修があれば、受講したいなと思いました。
・今回の研修では、実習の参考になる内容を学習することができた。また、講師の先生方も親切かつ丁寧に説明して頂き、とてもわかり易かった。3Dプリンターは、これからのものづくりに必要であり、CADソフトの使用方法も更に学習しなければならないと感じる。また、シーケンス制御についても、自動車を含め、機械のものづくりの知識に必要不可欠となってきているため、今回受講できてよかったと思う。最後に、学習指導要領の内容と評価についても大変参考になった。特に評価については、現在の自分の評価方法をもう一度再考しなければならないと思う。今回の研修で学んだことをこれからの指導に生かしていきたい。この度はありがとうございました。
標記講座は、前期、後期の2日間で実施しました。
前期は、授業改善の具体的な進め方に関する講義や授業改善プランを作成する演習等を行いました。
後期は、受講者の勤務校において、授業実践及び授業改善に向けた協議を行いました。

【受講者の感想】
・客観的な視点からの意見をもらい新たな自分自身の気づきとなりました。これからも、生徒がわかる授業のために授業改善を進めていきたいと思います。
・疑問に思うことを整理する機会となり、わからないまま進めてきたことを一旦見直すことができました。
・日々の授業で悩んでいることへ、現地研修を含めて個別にヒントをいただけて、充実した研修となりました。
・学級経営や授業を見直すための方法について、多種多様な方法を学ぶことができました。指導主事の先生方からいただいたアドバイスはどれも目から鱗で、自分の考え方が狭まっていたことを気づかせていただきました。
11月1日(金)、今日から始める保護者対応研修講座が開催されました。受講者は小学校4名、中学校10名、高等学校11名、特別支援学校8名、研究員2名、聴講者7名、合計42名でした。「保護者とのより良い関係のつくり方」の講義・演習が行われ、野々口先生の御講義やグループごとの意見交換などを数多く交えながら、望ましい保護者対応の手立てについて考え、効果的な方法を身につけることができました。
【研修内容】
講義・演習「保護者とのより良い関係のつくり方」
(講師)秋田公立美術大学 教授 野々口 浩幸 氏
・保護者対応を学んでみて、まずは私自身が子どもたちとどう向き合っていくのかが大切だと気づくことができました。子どもたちがどれだけ安心感をもって楽しく、園生活を過ごせるのかということ、そして園生活での取り組みをどのような形で伝えて行くのかということを私なりに考えて行きたいと思います。私も、子供たちの1番の応援者となれるような教育を目指したいと思いました。
・様々な資料やデータをもとにお話ししてくれたり、実際のエピソードを語ってくれたりしたので、印象に残りやすかった。現代のこどもやその保護者を、「自己評価が低く、承認欲求が強い」と表現していたことが印象に残った。自分も中学生の親世代なので、考えさせられた。今後、このようなこどもと親がさらに増えることが予想されるので、この講座を受けることが、学校課題解決の糸口になることを感じた。校内の教員間でこの講座での学びを共有し、職員室内の対話を増やしていきたい。
・色々な保護者がいる中でも、まずは保護者と積極的に関りをもつ機会を作ることが大切だと思った。学校で設定されている普段の面談だけでなく、PTA活動などを通じて、先生と保護者だけでなく、保護者同士の繋がりを作ることの必要性も感じた。
11月1日(金)に標記講座が開催されました。13名の受講者が被服分野の問題解決的な学習を取り入れた授業デザインについて研修を行いました。
【研修内容】
・「被服分野で身に付けさせたい資質・能力」について
・「指導と評価の一体化」について
・「問題解決的な学習」について
・ 被服実習体験
・ 授業デザイン


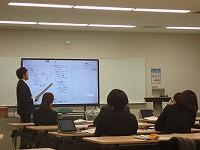
・実際にバックを制作してから被服製作の授業デザインを考えたので、より具体的に何をどのように改善すると問題解決型学習になるのか、とてもわかりやすかったです。調理実習と違って、被服製作は問題解決型学習にするのは、どうしても難しいという思いがあったのですが、考え方のヒントを得ることができました。特に、授業の最後の振り返りについて、目標の達成度とどうやって振り返させるかが、私の課題でもあったので、深く考える機会になりました。今日の講座は、大変勉強になりました。
・グループで授業デザインを考えることで、生徒への問いかけ方の新たな視点を得たり、自分の授業アイディアの根拠や目指すところを俯瞰して見つめなおすことができた。評価や改善の場面において、生徒にとって必要な発表か、活動か、という問いは深く心に残った。なんとなくの振り返りや共有ではなく、生徒にとっての必要感のある振り返りやグループワークを取り入れていきたい。
・家庭科の学習で、問題解決的な学習ができておらず、どのように取り組んだらよいのかも分からずにいたので、大変勉強になりました。また、中学校、高校との学習内容の繋がりも分かり、そこも考えていかなくてはならないと思いました。中学校、高校など他校種の先生方のお話を聞くことができ大変勉強になりました。製作もあり、楽しく学ぶことができました。