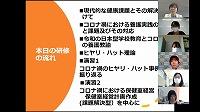B13 養護教諭研修講座
9月7日(火)・8日(水)、養護教諭研修講座がオンラインによる非集合型に変更して開催されました。受講者は小学校3名、高等学校2名、聴講者3名の合計8名でした。
1日目は、女子栄養大学 教授 大沼 久美子先生の「新型コロナウイルス感染症に伴う新しい保健室経営の在り方」と題し、「コロナ禍における養護教諭の実態と課題及びその対応」や「令和の日本型学校教育とコロナ禍の養護教諭」等について御講義を受け、「コロナ禍における保健室経営計画作成(課題解決型)」の演習を行いました。非集合型の研修ではありましたが、発表やグループ協議も行い、最後はグループに分かれて、実際に一つの保健室経営計画を作成してみました。講義の内容にあった、「保健室もGIGAスクール構想を導入し、ICT環境を活用する」ということをまさに体感しながら、学びを深めることができた様子でした。
2日目は、「D08 子供への緊急対応研修講座」と一部合同で行い、「学校における自殺予防」と題して、東京家政大学 名誉教授 相馬 誠一先生の御講義を受けました。様々な事例に対する相馬先生の御助言を聴き、子供の命を守る教員の役割について、真剣に考える機会となったようでした。
【研修内容】
(1日目)
講義・演習「新型コロナウイルス感染症に伴う新しい保健室経営の在り方」
女子栄養大学 教授 大沼 久美子 氏 ◆オンライン
(2日目)
講義・演習「中央研修会伝達」
青森市古川中学校 養護教諭 根上 あゆみ 氏 ◆資料提供
講義・演習「学校における子供の自殺予防」
東京家政大学 名誉教授 相馬 誠一 氏 ◆オンライン
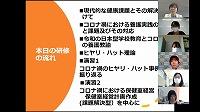

【受講者の感想から】
「新型コロナウイルス感染症に伴う新しい保健室経営の在り方」
・新しい生活様式に対応できるよう、自分自身も知識・技術をアップデートしていかなかければならないと感じた。また、一人で対応しようとせず、繋がりを生かして協力しながらコロナ対応にあたりたいと思った。ICTの活用はやってみたくても方法がわからない、知識がない等の理由で手をつけずにいたが、まずは実践することが大切だと感じた。
「中央研修会伝達」
・安全基地があるからこそ、安心して子供たちは行動を起こすことができるのだと学んだ。保健室で対応していると、バイタルサイン等の観察では問題ないが、我慢できそうでできない頭痛や腹痛が多く、対応に困るケースが多い。安心感を与える関わりや、子供の背景をしっかり理解する姿勢を大切にしながら関わっていきたいと考える。
「学校における子供の自殺予防」
・10~19歳の子供の自殺者数が増え続けていることに衝撃を受けた。何よりも「予防」を頭に入れ、子供たちの変化に敏感にアンテナを張り、見守っていきたいと思った。