
10月28日(火)に標記講座が開催され、小学校4名、中学校2名、高等学校6名、特別支援学校4名、計16名の受講者が「主体的・対話的で深い学びの視点を取り入れた消費者教育の授業づくり」をテーマに研修を行いました。講師の弘前大学 教育学部 教授 加賀 恵子 先生より、家庭科とパーソナルファイナンシャル・リテラシー、青森県の金融リテラシーの実態、教材・資料集の活用など、幅広く講義をしていただき、専門的な知識と明日からの授業に活かせる多くのヒントを得ることができ、とても有意義な時間となりました。
【研修内容】
講義・演習 学習指導要領における消費者教育
講義・演習 家庭科におけるパーソナルファイナンシャル・リテラシーに関する教材・資料集の活用
(講師)弘前大学 教育学部
教授 加賀 恵子 氏
講義・演習 主体的・対話的で深い学びの視点を取り入れた消費者教育の授業づくり
【講座の様子】
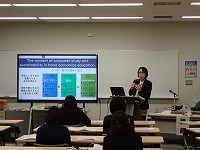

【受講者からの感想】
・3観点を意識した目標、評価について、学習指導要領に基づいた観点別の目標の立て方がとても参考になりました。改めて特別支援学校学習指導要領解説、教科編家庭を読み込み、目標につなげたいと思いました。午後の演習は、いろいろな授業の例や教材等を教えていただき、実際にやってみたいと感じました。八戸の消費生活すごろくは子どもたちも楽しんでできると思うので、言葉を簡単にしたり、金額を小さくするなどアレンジして使用できればと思いました。時間があれば自分たちで始めから作成も良いかもしれないと感じました。今後の消費者教育に関する授業作り、改善へつなげるヒントを得ることができました。
・午前の「学習指導要領を再確認する」は耳が痛かったです。読んでいるつもりになっていました。読み解くポイントを踏まえ、再度読み直したいです。本日は、色々と参考になる資料やサイトなどを紹介いただき、また試すことができて楽しかったです。また、小学校、中学校、特別支援と、それぞれがどんな力を身につけさせたいと思っているかの比較が見られましたし、それぞれの手立ての工夫も興味深かったです。家庭科って面白いですね。専門も迷いがなくていいですが、家庭総合・家庭基礎がやりたくなりました。ありがとうございました。
・普段、学習指導要領にじっくり目を通す機会がなかったので、系統性を意識したり考えたりしながら指導計画を作る活動が特に印象に残りました。八戸の消費生活すごろく、早速学級で使ってみました。お金の金額も大きく、子供たちは遊びながら、収入支出の大きさに一喜一憂しながら生活ではたくさんのお金を必要とすることや、クーリングオフや相談カードの使うタイミングについて考えていました。
10月31日(金)、今日から始める保護者対応研修講座が開催されました。受講者は、小学校4名、中学校5名、高等学校10名、特別支援学校9名、聴講者9名の計37名でした。講義や演習を通して、教員と子どもの信頼関係が保護者からの信頼につながることや、家庭や学校での愛着形成が子どもの健やかな成長にとって重要であることなど、実践的な内容を学ぶこと機会となりました。
【研修内容】
講義・演習「保護者とのより良い関係のつくり方」
(講師)秋田公立美術大学 教授 野々口 浩幸 氏
【受講者の感想から】
・野々口先生の魅力ある講義に惹きつけられ、あっという間の1日でした。愛着障害、良好な人間関係を保持するためのコミュニケーション力とバイアスの理解、保護者対応は複数で対応するなど、多くの学びと気づきがありました。また、自己成長エゴグラムやコミュニケーション力テストを行い、自分自身を見つめ、自己の課題を確認することができました。
・幼少期における愛着形成がうまくなされない場合、その後の発達や人間関係に何らかの影響が生じること、また社会に出てからの対人関係にも障害として現れる可能性が有ることを理解しました。近年では、学校への欠席連絡がアプリで完結するなど、教師と保護者が直接コミュニケーションをとる機会が少なくなってきています。そのような状況の中で、このようなテーマの講義は今後ますます必要になってくるのではないかと感じました。野々口先生の「チーム子育て」という考え方に大変共感するとともに、子どもだけでなく、保護者を理解し、共に教育を進めていくことの大切さを改めて実感しました。
10月28日(火)に、標記講座を開催し、12名の方が受講されました。講義「学習指導要領における伝統音楽指導」では、雅楽を聴いたり、唱歌で歌う活動を通して、伝統音楽の授業で育む資質・能力を捉えました。「表現から広がるこれからの学び」では、三味線に合わせ「秋田音頭」や「コキリコ」の民謡を歌ったり、「津軽じょんがら節」の三味線演奏を聴いたりして、郷土の伝統音楽について実感を伴った理解を深めました。午後は「さくらさくら」や「六段の調 初段」、「夏祭り」を教材として、箏の基本的奏法や唱歌について学びました。
[講座内容]
1 講義「学習指導要領における伝統音楽指導」
2 講義・演習「表現から広がるこれからの学び」
~我が国や郷土の伝統音楽を通して~
~唱歌や箏の活動を通して~
講師:梅屋楽器店 三味線講師 浅野 修一郎
箏講師 小野 玲子


【受講者からの感想】
・今回の研修では改めて伝統文化の素晴らしさや、生演奏の迫力や良さを実感した。民謡の発声一つにしても実演に叶うものはないと感じたし、三味線のバリバリ、ビリビリと伝わる空気感、箏を弾く際の指の動きなど、映像や音源では伝えられないものがあると感じた。
・講義では、伝統音楽の最終ゴールは何か(よさや愛着をもつこと)を確認することができました。また、学習指導要領に記載されている「音楽表現の共通性や固有性」を実感させるための授業例が非常に参考になりました。民謡の歌い方について、箏の演奏法の基礎、三味線の音色の魅力について実際に体験しながら学べることができて充実した研修でした。
・普段触れることが少ない音楽に触れられることは、インプットの機会が少ない教員にとって本当にありがたいと感じています。今回は実習ばかりではなく演奏を聴く時間がしっかりあったのが本当にうれしかったです。
10月27日(月)、28日(火)の2日間、標記講座を開催しました。小学校・中学校・特別支援学校の11名の先生方が受講されました。「特別の教科 道徳」の授業改善に向けて、基本となる考え方や様々な手法について、講義や演習を通して学びました。
【講座の内容】
1日目
・講義「考え、議論する道徳」の実現に向けて(全体会)
・講義・演習 ICTを活用したこれからの授業づくり(校種別)
・「考え、議論する道徳」の授業実践
(発表者)黒石市立黒石東小学校 教諭 菊池 哲子
県立弘前第一養護学校 教諭 髙橋 妹子
2日目
・講義・演習「考え、議論する道徳」の授業に向けた教材研究と発問
(講師)宇都宮大学 教授 和井内 良樹
・講義・演習「考え、議論する道徳」の授業構想(校種別)
【講座の様子】




【受講者からの感想】
・和井内教授の貴重な授業動画や指導案を拝見することができました。児童の机の配置、カードを使って順番を決めるやり方、発問の仕方、板書の書き方の手法等、丁寧に教えていただきました。私は、特別支援学校の教員なので、全てを真似することはできませんが、教師も子供とともに考える姿勢を大事にして、問題意識を共有していきたいと思います。
・道徳に対して、あれをやってみたい、これをやってみたいということが増えました。板書や発問、教材研究など、他の先生方の考えを聞いたり、センターの先生方から教えていただいたりと、大変充実した2日間でした。自分の学級の子供たちの実態を把握しつつ、新たなことに挑戦したいという意欲が湧きました。
・私の悩みは、子供の考えを深めさせる発問ができないことでした。しかし、今回の講座では様々な発問の仕方の他に、切り返し、問い返し、揺さぶり等の補助発問の重要性についても学ぶことができ、悩みが解決しました。これからの授業に生かし、発問を吟味し続けたいと思います。
・中堅研の授業研究で道徳を行いたいと考えているので、それに活かしていきたいです。また、日々の道徳の授業においても「授業づくりシート」を活用することによって、教材ありきではなく、内容項目・実態ありきの授業をしていきたいと思います。
10月28日(火)に標記講座を開催しました。
淑徳大学 教授の池畑美恵子先生をお招きし、「発達支援と教材教具について」と題して午前・午後を通して御講義を頂き、その後、演習「発達を促す授業の検討」を行いました。
発達の流れを理解するとともに、発達を促す教材教具の活用について学ぶ良い機会となりました。
【講座の内容】
・講義、演習「発達支援と教材教具」
講師 淑徳大学
准教授 池畑 美恵子 氏
・演習「発達を促す授業の検討」



(受講者の感想)
・教材の系統性は、著書で読んだことがあったが解説があったことでより分かりやすく勉強できた。また教授法に関して、用意すべき課題のステップやメッセージの出し方が参考になった。質のステップの変え方をいろいろ聞けてよかった。
・教材教具の活用の本来の意味とは、できることだけが目的ではなく、子どもの実態やつまづきが発見できることや教材があることで関係形成の糸口が見えることであることを学んだ。
・展示されていた教材が、そのまま使えそうなものもあり、真似て作ってみようと思った。そして、こどもの教材に対する反応を見極める必要があることから動画を撮るなどして丁寧に観察、見極めをしていきたいと思った。難しそうではあるが、メッセージの出し方も意識していきたい。