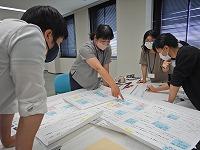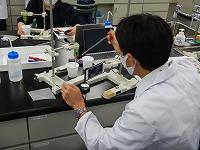8月25日(木)に標記講座を開催しました。小学校や特別支援学校の先生方が受講され、プログラミングの授業づくりについて学びました。
【講座の内容】
1.講義「小学校段階におけるプログラミング教育の在り方」
講師 国立大学法人電気通信大学 准教授 高木 正則先生
2.発表「自校におけるプログラミング教育」
発表者 六ヶ所村立千歳平小学校 横濵 和也先生
3.演習「プログラミングツールの演習」
【講座の様子】




【受講者の感想】
・この講義を聴く前までは、プログラミング教育に全く自信がない、しかし、目の前にいる児童達にやらなければいけないという葛藤がありました。実際に講義を受けて、自分自身が楽しみながら行うことが大事ということをおっしゃっておりました。教材の紹介もあったので、すぐに取り入れて児童達にも楽しみながら学ぶ環境を作りたいと感じました。
・発表者の方が、大変謙虚な方で、私と同じ目線に立ってくれているようなお話で、やってみようという気持ちになった。まずは、今回学んだ教材を時間があるときにいじることからやっていこうと思う。
・演習の時間が足りなく感じるほど、大変内容が盛り沢山であったが、その分、実際にビスケットやスクラッチ、マイクロビットに触れながら演習を通して学ぶことができたことが、この演習の一番の収穫であった。また、様々なプログラミングコンテンツ等を知ることができたので、自校でも紹介して活用を図っていきたい。
・講座の目標である、プログラミング教育への理解と、技能・指導力の向上に大いに結びついた。昨年度に引き続き、本研修講座に参加したが、自分自身を更にアップデートできる内容だったことに大変満足している。特に、プログラミングツールの演習については、時間の都合で急ぎ足な所もあったので、もっと時間が欲しいと感じた。次年度の希望としては、講義よりも演習の時間を更に長く設定していただけたらと思う。
・自分の未熟さ故に、講義や演習の成果を十分にものにできたかは分からないが、少なくとも受講前よりもICT、プログラミング教育の取り組みに対する危機感を強めるとともに、自分の知識・スキルともに高まったと思う。率直に、もっと学びたい。ありがとうございました。
8月29日(月)県立学校事務長研修講座(後期)が開催され、県立学校の事務長9名が受講しました。事務長の職務と役割についての講義を聞き、学校事務室経営について協議を行いました。各学校の状況を共有することで、諸課題への解決へ向けた方策を探られた様子でした。
【研修内容】
講義「事務長の職務と役割について」
講師 県立三本木高等学校 事務長 齋藤 慶仁
協議「学校事務室経営について」
助言者 県立三本木高等学校 事務長 齋藤 慶仁
助言者 県立七戸養護学校 事務長 工藤 東輔
【受講者の感想】
・先輩事務長が心がけていることや実践していることを聞くことができ、大変参考になった。
・日頃話せないこともこの講座で情報交換することにより、事務長職としてどうあるべきかが少し見えてきた。
・各校の事務長の考え方や事務室内、学校内のより良い環境づくりや雰囲気づくりを聞き、今後の参考にしたい。
8月19日(金)標記講座を開催しました。
甲南女子大学村川雅弘教授を講師に招いて、講義・演習を行いました。
校内研修でのワークショップ型の協議会のもち方やグルーピングの仕方などの
具体的な研修方法や、カリキュラムマネジメントの視点で校内研修を見直し、
次年度の計画を作成していく方法など、校内研修を活性化するための多くの方法を学びました。
【講座の内容】
講義・演習「カリキュラムマネジメントと校内研修」
演習・協議「校内研修プランの見直し」

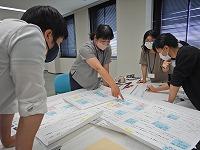
【受講者の感想】
・今日の講義を受けて、受容的な関係があるからこそ主体的、対話的で深い学びを育成していくことができると改めて学ぶことができました。そのためには、横断的な視点で教科を見直し、組織的に配列していく必要があることも再確認できました。学級でも校内研修でもワークショップ型のいろいろな方法を使って、再度挑戦していきたいと思いました。
・教員の意識が変わる校内研修を実施していかなければならないと改めて感じました。そして、生徒の好ましい成長のためには教員の学ぶ力が必要であり、これからも私だけでなく教員全員がやりたいと思えるような研修を計画・実施してきたいと思いました。特に、生徒を校内研修に巻き込む実践を取り入れてみたいと思いました。
・冒頭の「カリキュラム・マネジメントとは目標と方法のベクトルを揃えることである」という言葉が非常に印象に残り、頭がスッキリしました。校内研修を進めるに当たってたくさんのアイディアを頂き、お話をききながらやってみたいことがたくさん出てきました。様々なことにトライし、自分自身でKPT法等を用いて振り返ってみたいと思います。
8月23日(火)と24日(水)の2日間、C20 学びを実感させる高等学校理科実験講座[化学]が開催され、5名の先生方が受講しました。 生徒の興味・関心を引き出すための演示実験や思考力・判断力・表現力等を高める効果的な実験等を通して、学校現場での活用方法を模索し、授業力の向上を図りました。1日目:理科の見方・考え方を働かせる授業デザイン 身近な素材を用いた実験とその教材開発2日目:単元を貫く観察・実験を取り入れた授業づくり 思考力・判断力・表現力等を引き出す実践とその工夫


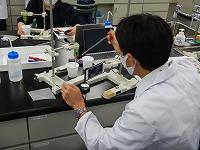

【受講者の感想】
・指導要領解説の観察、実験の一覧から今までできていなかった単元が分かり、機会があれば取り組んでみようと思った。実験においてGoogleを用いた個別学習、協働学習ができることが分かったので、学校の環境が整ったら利用したい。粒子とすき間の実験は、密度の理解、粒子の大きさ、水素結合を学べるため、3年文系の生徒でも大変有用だと思った。コロイドの性質では、モル濃度の違いで沈殿、正、負コロイドの粒子の大きさ等の違いを簡単に実感できるため、まずは演示で生徒の反応を見てみたい。さらに凝析もできるのなら続けてやって、印象付けたい。
・牛乳と墨汁を用いてブラウン運動を観察した。墨汁ではなかなかブラウン運動を見つけることが出来なかったが、最終的には何を見つけると正解なのかがわかったので、授業でも実施する自信がついた。エントロピーシュミレータについては、そのねらい、考察を自分自身が今後さらに勉強し理解しなければいけないと感じた。醤油を用いた沈殿滴定では、滴定の操作の再確認や、色の微妙な変化の確認ができて良かった。糖類の実験で、反応を実際に目で確かめることの重要性と楽しさを実感できた。
・日々、時間や手間をかけずに簡単にできる実験をやっていますが、単元によって実験を多くできるところとあまりできないところがあるので、今回の講座で学んだものを1つずつ実践していきたいと思いました。ありがとうございました。