
7月24日(水)に標記講座を開催しました。技術分野を担当する中学校および特別支援学校の先生方が受講され、技術分野の授業づくりについて学びました。
【講座の内容】
1.講義「技術分野の現状と課題」
2.実習「はんだづけ、TinkerCadの基本操作について」
3.演習「電気機器の設計・製作」
【講座の様子】


【受講者の感想】
・Tinkercad,ブレッドボード,はんだ付けなど実践的なお話が多く、エネルギー変換の技術に対してに苦手意識が軽減されました。大変参考になりました。講座で学んだことを早速実践したいと思います。大変有意義な講座ありがとうございました。
・今年度初めて技術の授業をもって、指導の仕方が難しいと思っていたのでとても参考になった。また、技術には元々興味があり、普段から自分の生活の中で行っていること(クルマのフットライトを取り付けたり、木材で棚を作ったり、スマート家電を効果的に使用したり)を授業に反映できるので更に技術の必要性と楽しさが深まった。
・課題解決の授業については、本来個々の課題に取り組ませていく必要がありますが、キット教材で済ませてしまうというのも現状です。まだまだ検討していかなければならないこともありますが、キット教材の活用の仕方を工夫しながら課題解決に向かう授業を検討し、計画的に実践していきたいと思います。
・エネルギー変換、とりわけ電気の分野は、自分自身中学校で学んだことがなく、十分な基礎知識がないまま、はんだづけについての技能の習得に重点を置いて取り組んでいました。今回ブレッドボードやTinkerCADを用いた演習で、初めてのこともあり難しさも感じましたが、受講前よりも見通しをもつことができるようになりました。
全然詳しくなくても演習を通してイメージをもち、実際の作品制作やアイディアにつなげるというこのプロセスは生徒にとっても非常に重要な要素だと感じました。
・授業場面になった時に、また、授業を計画する時に、教科書と生徒の実態を照らし合わせ、内容の選択・精選が難しいと思い、受講しました。様々なアイデアに触れさせていただき、参考になりました。
7月23日(火)に校長研修講座(後期)が開催されました。今年度は、講師として広島大学大学院教授 曽余田 浩史 氏をお迎えして研修を行いました。曽余田教授は、独立行政法人教職員支援機構でも研修を運営なさるなど、幅広く御活躍されており、有意義な研修となりました。日程は、以下の通りです。
午前・午後 講義・協議「学校の組織力とスクールリーダーシップ」


・学校課題をどう解決していくか熟考し、校長として明確なビジョンやミッションをもち、それを常日頃から発信していく必要性を強く感じました。
・学校運営をするときに、戦略的に行うことが大切であることを確認できました。学校の質的発展を意識して、「自分たちはどのように歩んできて、現在どこにおり、これからどこへ向かうのか」に目を向け、教職員が同じ方向を向くように舵をとりながら経営していくことが校長しての職務であると実感しました。
・自分一人ではなく、先生方の意見や保護者や地域の願い、子ども達の思いを汲み取っていき、本校の役割を考え直してみたいと思いました。
7月23日(火)、24日(水)に標記の講座を開催しました。
1日目は学習指導要領の趣旨に基づき、身近な素材を用いて探究の過程を意識した観察、実験に挑戦しました。
2日目は、浅虫海洋生物学教育研究センターで岩﨑藍子助教と福森啓晶助教による講義、実習、実験を行いました。地元の陸奥湾の生態系について、生物の機能に着目してプランクトンを分類し,捕食者である貝類を観察、解剖することで生物多様性について深く考えることができました。
〔講座の内容〕
・理科の見方・考え方を働かせる授業デザイン
・身近な素材を用いた観察・実験とその教材開発
・地域の素材を用いた観察・実験とその教材開発
・地域の素材を活用した授業実践とその工夫

・指導と評価の一体化が難しいと考えていたが,実験,レポートなどを上手に組み立てて,3観点をそれぞれ見ていくイメージで進めるとよさそうだと感じた。
・わずかな濃度の違いで結果が変わることも体験でき,予備実験の大切さを知った。一方で,なぜ結果が予想と異なるのか生徒に考えさせることも重要だと気付くことができた。
・プランクトンの同定では,知らない生物がたくさんあり,調べながら学んでいくことができた。分類や形態は普段の授業では説明だけで終わっているところがあったので,今回の経験を今後生徒に還元したいと思っている。
・分類などは興味を持ちにくい分野だと思っていたので,今日の実習で自分の意識改革ができて良かった。
・改めて実験することの大切を実感した。まずは手軽に実施できそうな実験から取り入れ,少しでも多く,実験の機会を生徒に経験させていこうと思う。
7月24日(水)に寄宿舎指導員研修講座を開催いたしました。
今年度は15名の寄宿舎指導員の先生方が受講されました。
学校教育課主事による教職員の服務についての講義の後、青森大学 教授 船木昭夫先生を講師に迎え、午前中はメンタルヘルスを中心に、ストレスへの対処行動(コーピング)についてとソーシャルスキルズ・トレーニング(SST)の意義について、午後は障害特性を踏まえた金銭管理の支援について、演習を交えながら、学びを深めることができました。
また県立青森第二高等養護学校 秋元 彩未 先生より「寄宿舎指導員としての私の実践」という内容で、ご発表いただきました。
最後に、学びを深く理解するために、各自で講義・演習、発表内容を振り返り、グループで共有しました。


【受講者の感想】
・ストレスへの対処行動、コーピングの概念を知ることで、ストレスとうまく付き合っていけそうな気持ちになりました。
・特にSSTの意義については、指示をするのではなく、一緒になって活動をしていく支援者としての心構えやアプローチが大切だと思いました。生徒との活動に生かしていきたいと思います。
・「当たり前を褒めること」を少し忘れかけている自分がいたので、思い出せてよかったです。特に、小学生は当たり前ができるように努力していると思うので、どんどん褒めていこうと思います。
・舎生とかかわる上で心がけていることについて、今後の実践で生かしていきたいと思いました。
7月23日(火)に標記講座を開催しました。
県立学校から6名の先生方が参加されました。
Active Directory(AD)を用いて校内のファイルサーバーを管理する方法について、「仮想化技術」を活用して1台のパソコン上にWindows サーバーとWindows クライアントの画面を並べて実習を中心に学びました。
【講座の内容】
1章 ユーザー・グループの管理
2章 アクセス権の設定
3章 バックアップとリストア
【講座の様子】


【受講者からの感想】
・私はまだシステムの管理はしていないが、いずれやることになるかもしれないということで今回受講した。サーバーと聞くとエンジニアの領域を想像していたが、思っていたよりは理解しやすく、今回で大まかなことはつかめた気がするので、本当にやることになったらもう少し勉強を深めて取り組んでみたい。
・これまで自信がないまま、引き継ぎで教わっていた操作の理由(なぜこの設定が必要なのか)などを確認する場となり、大変参考になりました。次年度以降も本講座のような内容をぜひ継続していただけると幸いです。
・ユーザーやグループの作成から管理、また、フォルダのアクセス権の設定の仕方、バックアップ等、知りたい情報や技術を学ぶことができて、大変有意義な時間となりました。校務外部ファイルサーバーの仕組みも分かりましたので、本校にある既存のサーバーの整理をしてみたいと思います。
7月12日(金)C22 時間的・空間的な関係を探究する理科野外実習講座[地学]を深浦町の十二湖周辺の研修地で開催しました。弘前大学教育学部准教授の田中浩紀氏を講師に迎え、大戸瀬駅裏海岸で海食台及び大型有孔虫をはじめとする多くの浅海性生物の化石を観察し、ガンガラ穴の露頭では流紋岩を観察しました。その後、車窓から日本キャニオン及び大崩を遠望しました。白神十二湖エコ・ミュージアムでは、立体地形模型で海岸段丘の成り立ちを確認し、大戸瀬海岸の泥質砂岩から化石の有孔虫殻を取り出し観察・同定を行いました。受講された先生方は、講義・実習を通して、西津軽郡海岸の形成過程についてじっくり学び、考えることがことができたものと思います。
〈受講者の感想〉
・採取したコケムシの化石、泥質砂岩から検出・同定した有孔虫化石、ガンガラ穴が流紋岩からできていること、日本キャニオンが凝灰岩からできていることなどは授業実践に活かせると思った。
・とても有意義な研修であり、生徒にも紹介したい内容であった。
・海岸での資料採取や、有孔虫化石の観察においても、資料や実物を見せてもらうことで、興味・関心が高まり、集中して作業することができた。
・校外での学習で、石や地面を見て、様子の違いに興味・関心を引かせることができると感じた。
7月10日(水)~11日(木)に標記講座を開催しました。
1日目は講義「「読むこと」指導の授業改善」を行い、指導事項がぶれない授業づくりが大切であることを確認しました。また授業実践についての協議やICT活用の演習を行いました。
2日目の宮城教育大学の児玉忠教授による講義「「深い学び」の実現に向けた国語科授業づくり」では、説明的文章における授業づくりについて授業改善の視点を学ぶことができました。


【受講者の感想】
・出席した先生方と悩みを共有し意見交換したり、御講義を聞いたりすることで授業で挑戦したいことが多く見つかりました。
・「言葉による見方・考え方」の捉え方や、「主体的に学習に取り組む態度」の評価の仕方など、これまでぼんやりとしか捉えていなかったものが、明確になりました。
・児玉教授の御講義では、学習指導要領のキーワードや実践的な内容に関して、現場のことを深く理解してくださった上で様々な手立てを紹介していただいたので、すぐにでも現場で活かせそうな内容ばかりでした。
7月4日(木)、5日(金)の2日間、標記講座を開催しました。
【講座の内容】
(1日目 所内)
◇講義:「指導と評価の一体化」について
◇講義:高等学校における農業教育について
講師:県立三本木農業恵拓高等学校 校長 小泉朋雄 氏
◇講義:青森県の農福連携の取組について
講師:県農林水産部構造政策課 担い手育成グループ
ユニバーサル農業推進プロジェクトチーム 主幹 古川耕一郎 氏
(2日目 所外 法人・企業視察)
◇視察:県内企業の農福連携の取組
講師:一般社団法人 日々木の森
代表理事 立崎文江 氏
◇視察:県内企業の農福連携による経営活動
講師:有限会社 金子ファーム
取締役会長 金子春雄 氏
【講座の様子】


【受講者の感想】
・農業を楽しいと思ってもらえる授業づくりを行える教員になりたいと思います。
・指導と評価の一体化では、単元指導計画の重要性が理解でき、生徒に何を身につけさせ、どのような手立てで評価をしていけばよいかを考えることができました。
・ICTでは、Googleサイトの使用方法を効果的に教えて頂き、ペーパーレスに繋がる小テストや、単元確認テストの実施によって生徒の振り返りに繋がる大切なツールになると確信しました。早速、現場での指導に取り入れます。
・農福連携に取組む企業視察は大変勉強になりました。魅力を伝えたいという高校生の心の動きが見えました。農業教育の面白さは人との繋がりの中にあると思いました。
・農福連携の講義を通して、新たな知見を得られたことはもちろん、生徒の主体的で対話的な深い学びの実現に向けた活動のヒントとなることが多く見つかりました。
7月10日(水)、標記講座を開催しました。
小学校、中学校、高等学校など多数の校種の先生方が受講しました。
【研修の内容】
日本大学 教授 熊谷 圭二郎 氏 を講師に迎え、「よりよい学級(HR)集団づくり」というテーマで、コーチングやリフレーミングなどの演習を交えながらご講義いただきました。講義では、「教師の役割の変化と学級経営」「学級集団づくりのためのカウンセリング的かかわり【安全安心】」「子どもの主体性を育成するコーチング的かかわり【活性化】」の3つの観点で、児童生徒との信頼関係構築の理論や児童生徒相互の好ましい人間関係づくりを支える手法や実践について、分かりやすく解説していただきました。


【受講者の感想】
・今年初めて担任を持ち、HRづくりに関して悩むところが多くあったのですが、熊谷先生の講義やアクティビティを通して本当に多くの気づきをいただけました。校種の違う先生方とお話できたこともありがたかったです。「いいとこ探し」は必ず実践したいと思います。自分自身も生徒の気になる部分をルフレーミングして、捉え方を変えてみたいと思います。
・今必要とされている、あるいはこれから必要とされる教師の役割について、理解を深めることができました。また、今の子どもたちは思った以上に人との関わりが希薄だったり、関係づくりに課題を抱えていたりすることが分かりました。だからこそ、授業力だけでなく集団づくりや学級経営のスキルを身に付けることや、人間性を磨くことが大切であると感じました。
・子どもたちが多様化し、これまでの経験だけでは上手くいかないことが増えていると感じていました。新しい学びが多く、生徒、保護者とのより良い関係づくりにつながると思いました。新しい学びを取り入れ、ミドルリーダーとして世代間や管理職とをつなぎ、学校運営に貢献したいと思いました。
7月9日(火)、10日(水)の2日間、商業教育指導者講座を開催しました。
9名の先生方が受講し、学習指導要領が求めるビジネスの視点からの授業のヒントを数多く得ることができ、大変有意義な講座となりました。
【講座の内容】 9日 学習指導要領 教科「商業」について
ビジネスゴールを達成するWebマーケティング戦略
株式会社 コンシス
代表取締役 大浦 雅勝 氏
10日 ビジネスにおける資産形成とリスク管理
R&C株式会社 青森支社
セミナー推進部 マネージャー 石澤 枝美子 氏
主体的・対話的で深い学びを実現する授業デザインの構築
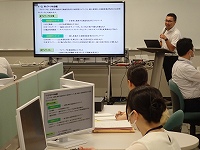

【受講者からの感想】
・実際にビジネスを知る人の講義を受けられるのは大変うれしく、勉強になると感じました。授業に生かすために学校に帰ってから授業の準備をしたいと思います。ありがとうございました。
・学習指導要領の趣旨を理解することで、授業デザインの可能性が広がったように感じる。実際のビジネスを学ぶことで、教科「商業」の面白さや魅力をさらに感じることもできた。私たちは幅広い分野の商業科目を担当するため、どの科目でも「ビジネス」を感じさせ、またその魅力を伝えられるようにしていきたい。今回は学習評価についても学習したため、「思考力・判断力・表現力」や「主体的に学習に取り組む態度」をどのように評価していくことが生徒・教員にとってよいものかを考えていきたい。
・とてもとても満足です。二日間時間があっという間に進みました。この研修に参加しなければ生成AIも使うことがなかったです。こんなに便利なものを知らなかった自分が恥ずかしいです。これからは自分から情報収集すること、実際に試してみることを心掛けます。
また、これからの授業の進め方・やり方についても考えていかなければと危機感を持っています。インプットアウトプットの割合を4対6に少しでも近づけていきたいと思います。
本当に学びの多い二日間でした。ありがとうございました。
7月11日(木)、標記講座を開催しました。
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の先生方が受講しました。
横浜国立大学 准教授 神山 努 氏 を講師に迎え、「本人・保護者の思いに寄り添う教育相談」「子供と保護者をポジティブな視点で支援する」というテーマで、演習を交えながらご講義いただきました。講義では、幼児児童生徒の行動上の問題状況を分析する方法やそれを踏まえた行動支援の方法について分かりやすく解説していただきました。
また、担当している幼児児童生徒の気になる行動について分析し、行動支援を検討する演習は、すぐに実践に生かすことができる内容だったため、大変好評でした。

【受講者の感想】
・クラスにも気になる子がおり、今日学んだ行動分析や、適切な行動を伸ばしていく支援の方法などを実戦に生かしていきたいと思いました。
・子供の問題行動に注目しがちですが、子供ができている点については当たり前だと思って、褒めることをしていなかったと気付かされました。子供を褒めるチャンスを見逃さないでいきたいと思います。
・現在、特別支援教育コーディネーターとして、様々な生徒・保護者と関わってきたが、なかなか予防の視点からできていませんでした。また、環境を変えることで生徒の問題行動を変えることができると知り、早速実践していきたいです。
7月2日(火)、3日(水)の2日間にわたり、高等学校英語科言語活動実践講座を開催しました。具体的な言語活動の事例を用いて、授業デザインの構築について演習・協議を行いました。また、生徒の言語活動を充実させるための働きかけや学習支援についても参加者同士が活発に意見を交わし、様々な発見や活動への深い理解があったように思われます。
【講義内容】
1日目:「生徒の英語運用能力を育成する言語活動の実際」
講師:県立青森高等学校 教諭 當麻 進仁
2日目:「効果的な言語活動の実現に向けて」
講師:1日目と同じ
【講座の様子】
【受講者からの感想】
・具体的な活動を生徒役として体験することができたので、大変わかりやすかったです。活動の順番について考えることは大事だと学びました。教科書に沿って進めていくだけが最善とは限らないということにも気づかされました。
・様々な活動を通して、生徒の英語力に応じた配慮をする必要があると感じた。スライドで活動の方法を提示するだけではなく、目的やその場の生徒の取り組む様子を日頃から観察することから意識してみようと思う。
・生徒への支援の仕方を考えていく必要があると感じた。また、生徒の学力差が大きい中で、教材の工夫も考えていきたい。
・授業の展開について細かく分析し、学ぶことができました。特にリスニングの方法は今後の授業に役立てていきたいと思います。
・授業の活動次第で授業を楽しくすることができるのだと、今回の講座で初めて実感できたので、今後の授業改善に活かしていきたいです。
6月28日(金)芸術系教科の資質・能力を育む授業づくり講座を開催しました。4名の先生方が受講され、校種・科目等をこえて芸術科が育むべき資質・能力についての講義後、題材構想と指導と評価の一体化を意識した授業づくりの演習を行い、最後に模擬授業や発表をしていただきました。
【講座内容】
1 講義・演習「芸術科が育む資質・能力について」
講師 県総合学校教育センター 指導主事 野呂 俊光
指導主事 道川 里奈
2 演習 「資質・能力を育む授業づくり①」~単元・題材構成の工夫~
3 演習 「資質・能力を育む授業づくり②」~指導と評価の一体化について~
【講座の様子】


【受講者からの感想】
・同じ芸術科目でも、校種や教科が違うと、気をつけるべきポイントや指導の重点が大きく違うことが興味深かった。その違いから気づけることや学びもたくさんあり、今後の指導に活かしていきたい。
・生徒にどのような資質・能力を身につけて欲しいのかを自分自身で考えながら、授業に取り組んだり、授業改善を行いたいと思いました。