
6月22日(木)~23日(金)に標記講座を開催しました。
1日目は講義「「読むこと」指導の授業改善」を行い、言葉に着目し丁寧に内容を読み取る学習指導が大切であることを確認しました。また授業づくりについての協議やICT活用の演習を行いました。
2日目は岩手大学の藤井知弘教授による講義・演習「「深い学び」の実現に向けた授業づくりの考え方」「「深い学び」を実現する授業づくり」を行い、授業づくりについての大切な視点を学ぶことができました。
【受講者の感想】
・授業の進め方やICT活用など、授業改善への気付きが多くありました。
・藤井教授の講義では「初めに学習者ありき」という言葉がとても心に残りました。生徒がどのような知識をもっていて、この単元ではどのような力を身に付けさせたいのかということを明確に把握し、授業づくりを行う必要があると改めて感じました。
・協議では同じような悩みや実践例を共有することができ、今後への見通しをもつことができました。
6月26日(月)に標記講座を開催しました。中学校、高等学校、特別支援学校の先生方が受講され、Web会議システムを使ったオンライン授業の仕方、動画共有サービスやクラウドサービスの活用について学びました。
【講座の内容】
1.「個別最適な学びの実現」とオンライン授業
2.オンライン授業における著作権
3.Web会議システムを利用したオンライン授業
4.動画共有サービスを活用したオンライン授業
5.クラウドサービスを活用したオンライン授業
【講座の様子】


【受講者の感想】
・Zoomのホスト側の操作や、YouTubeを活用した動画配信について知ることができたので良かった。Zoom自体は活用したことがあるが、参加するだけで自身がホストになることはなかったので、とても参考になった。また、YouTubeチャンネルの活用については、講習や教科指導で使いたいと考えていたので、実践するための知識を得ることができた。YouTubeにおいて、ライブ配信を使ってリモートの授業をすることは可能なのか気になった。ロイロノートについてはまだまだ理解が乏しいので、個人的に検索するなどして勉強したい。今日の学びを今後の教科指導等に活用していきたいと思う。
・Zoomでのオンライン授業やYouTube配信(チャンネルの作成等)の仕方がわかり、目的は達成できたと思います。学校に戻りましたら、とりあえずチャンネル作成をし、音声動画を一本作ってみたいと思います。現在はパドレットで生徒同士の意見交換をしていますが、ロイロノートの共有も試してみたいと思います。ご丁寧に説明して下さり本当にわかりやすかったです。ありがとうございました。
・不登校生徒とのやりとりを増やす糸口になればと思い、受講しました。ICTは苦手分野ですが、Zoomは思いのほか、自分でもすぐにできそうだなと思えたので、実践していきたいと思います。ロイロノートを使うに当たっては、現在担当している学級では文字入力等の課題がありそうだと感じたので、ICTを使用することで、教師にとっても生徒にとっても効果がありそうなところで使っていけたらと感じました。
6月20日(火)、21日(水)に標記講座を開催しました。11名の先生方が参加し、今年度から県立学校に導入されるNetCommons3の操作方法について、実際にサンプルサイトを作成しながら学習しました。受講された先生方は、CMSを活用したWebページ運営について具体的なイメージを持つことができた様子でした。
【講座の内容】
20日 CMSとNetCommons3 21日 プラグインの応用的な利用
設定・管理画面 ファイル転送
基本ページの作成 総合演習
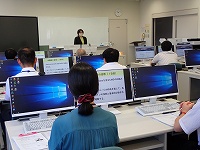

【受講者の感想】
・私自身、今までのイメージは、学校ホームページは担当者がやるもの、というイメージでした。その中で、今回の研修を受け、誰でも非常に簡単に編集することができ、研修を受けていない教員にも伝えやすいと感じました。
・NetCommons2から3への更新作業に向けて、操作方法や特徴について知ることができました。基本的な部分からの説明で非常にわかりやすかったと感じました。学校に戻り情報を共有しながら更新作業を進めていきたいと思います。
・ホームページ作成の際の方法を学ぶことができました。レイアウトなど学校の特色が出るようなページを作成できればと思います。
6月13日(火)に標記講座を開催しました。14名の先生方が受講されました。
午前は、ICTを効果的に活用した授業づくりの考え方や例についてお話をさせていただきました。また、「わたしの実践発表」では、十和田市立北園小学校の川村比査子先生に、日頃お取り組みになっている貴重な実践を紹介していただきました。発表後にたくさんの先生方から御質問をいただき、充実した時間となりました。
午後は、東京学芸大学の粕谷恭子教授に講義をしていただきました。英語を学ぶ上で大切なことを分かりやすく教えていただき、あっという間の3時間となりました。講座の中で「意味が音を出す」「意味と音を結び付ける」など、目的や場面、状況などに応じた英語使用の大切さについて触れられていたのが印象的でした。
【講座の内容】
・ICTを活用した外国語・外国語活動の授業づくり
青森県総合学校教育センター 指導主事 長谷川 紘一
・わたしの実践発表
十和田市立北園小学校 教諭 川村 比査子
・外国語・外国語活動の指導の在り方
東京学芸大学 教授 粕谷 恭子
【受講者からの感想】
・2つの講義と実践発表を通して、総合的に英語の授業づくりに関する技術や考え方を得ることができました。
・本研修を受講して得られたことが大変多かったです。受講者との話し合いも有意義でした。早速明日からの指導に生かしていきたいです。
・外国語の授業改善につながるたくさんの考え方や、具体的な事例を教えていただいたので、明日からの授業に役立てていきたいです。
・小学校における外国語の学習の重要性、教師の働きかけ方などを講義や演習を通して体験することができました。
・学習の組み立てのヒントをたくさんいただきました。
・外国語におけるICT機器を使用した授業づくりを学ぶことができました。また、日々の自分の指導を振り返り、改善点を考えることができました。
6月20、21日に中学校理科実験講座が開催されました。定員16名でしたが、受講された先生方の人数は13名となり、活気あふれた講座となりました。地区によっては、中体連の振替休日にも関わらず、講座に参加された先生方もいました。日程は以下の通りです。
6月20日(火)午前:講義 「理科授業改善の視点」
午後:講義・実験「授業で使える観察・実験の工夫」
(2学年1分野の内容)
6月21日(水)午前:講義・実験「授業で使える観察・実験の工夫」
(3学年2分野の内容)
午後:講義・実験「授業で使える観察・実験の工夫」
(1学年2分野の内容)
参加された先生方の感想の一部は「続きを読む」からご覧ください。
・実験講座で望ましい結果が得られる方法をたくさん学ばせていただきました。特に驚いたものはマグネシウムの酸化実験と、花粉管・体細胞分裂の実験です。教科書には載っていなく、しかも手軽に実験できる方法を教えていただきました。ぜひ今回の講座で学んだ内容を学校に帰ってからも生かし、生徒に実験させてあげたいと思いました。
・毎年大変お世話になっておりますが、何度参加しても飽きることなく2日間有意義な期間を過ごさせていただいています。本年度紹介していただいた観察・実験内容、撮影できたデータは、早速学校に戻り次第授業に生かせそうです。また、本校の理科教員にも情報を共有し、授業改善に役立たせることができそうです。
・今回の講義では、身の回りのものを工夫して使う実験の方法を学ぶことができました。特に、磁界の実験では、3Dで磁界を見せることができる方法を知ることができたので、実践してみたいと思います。また、実験室自体にも他の単元に関するヒントが沢山ありましたので、自分なりに創意工夫を凝らしていきたいと思います。
6月14日(水)、標記講座を開催しました。
小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の先生方が受講しました。
筑波大学附属桐が丘特別支援学校 教諭 佐々木 高一 氏 を講師として「カード整理法による実態把握の進め方」というテーマの下、講義・演習を行いました。演習を通して、児童生徒の実態把握の進め方について体験的に学ぶとともに、実践のポイントについて分かりやすく教えていただきました。午後の演習では、午前の講義・演習を受け、児童生徒の実態の整理を行いました。
また、午後の協議「自立活動の指導の充実に向けて」では、グループに分かれ、児童生徒の指導の経過や指導上の課題(悩んでいることなど)について、情報を共有し、対応策を検討することで、日頃の実践を振り返る機会となりました。


【受講者の感想】
・指導すべき課題を挙げる方法を、演習を通して学ぶことができ、大変参考になりました。
・書き出してみると、広い視野でその子を捉えられました。グループ分けによって頭が整理できました。全ての一つ一つの現象に対応するのではなく、もとになっている大きなもの(要因)に気付いて手立てを考えられれば、すぐ結果を出そうとする焦る気持ちが鎮まり、長期的に取り組めると思いました。
・先入観を持たず、事実から解決策や対応策を導いていくことの大切さを現場で生かしていきたい。
6月12日(月)標記講座が開催され、36名が受講しました。小・中学校と違い、教科としての道徳がない高等学校においてどのように道徳教育を進めて行けばよいのか理解を深められた様子でした。
【講座の内容】
講義「高等学校における道徳教育の推進」
講義「小・中学校における道徳教育の実際」
発表「本校の道徳教育」
演習・協議「自校の特色を活かした道徳教育の展開に向けて」


【受講者の感想】
・道徳教育は道徳性を育む事が目標であり、小中の道徳科の評価では、道徳性の成長をみとるという点が新しい気付きでした。日頃、道徳的実践を重視しすぎていたと気づきました。生徒指導的観点から、道徳的実践を強要していたのかと反省しました。考えさせること、生徒の内面を推し量ることを心がけたいです。
・高校で道徳教育を行おうとすると、とてもハードルの高いもののように感じていました。しかし、実際は一から新しいことを始める必要があるわけではなく、これまでの先生方の取り組み一つ一つが実は道徳教育だったのだと実感することができました。それは、学校の教育目標に繋がるものでもあるはずなので、今回の研修を受講した自分自身ができることから取り組みを始めてみたいと思います。
・説明の一つ一つが丁寧でわかりやすかった。各教科とのつながりも、事例を挙げつつ説明がなされていたので、理解を深めることができた。授業はもちろん通常の学校生活の中で道徳教育の内容項目を意識していきたい。
・普段の教育活動が道徳教育の実践になっていることを知り、安心した。このことが学校全体で共有されていないように感じた。特別な何かではなく、今行っていることを「見える化」するという次のステップに組織的に進めるように工夫をしたい。
6月9日(金)標記講座を開催しました。県立学校の農業・工業・情報・商業の先生方9名が受講され、本県における産業の現状と展望について2事業所の方から講義を受け、実際に所内や店舗を視察させていただきました。
【講座内容】 本県における産業の現状と展望(講義・視察)
午前 株式会社ジョイ・ワールド・パシフィック
代表取締役 木村 祝幸 様
午後 紅屋商事株式会社(視察先:カブセンター神田店)
取締役SM事業部 部長 秦 武史 様
【講座の様子】


【受講者の感想】
・沿革を聞き、資金集めの大切さを理解しました。何かを行うためには当然人とお金、技術が必要でそれをどのように集め、維持していくのか、また将来を考え、何に挑戦すべきかなど、難しいことが沢山ありました。経営学や経済学を希望する生徒に伝えていきたいです。
・1つ製品が完成して終わりではなく、そこから新たな挑戦をしているということや、変化を恐れず様々な事柄に挑戦することで新たなビジネスチャンスをしていると感じました。教科商業単独で取り組むより産業教育全体で取り組むことで、新たな学校教育の場が見えてくると感じました。農業や工業とのコラボも考えていきたいと思いました。
・紅屋商事株式会社様の売場づくりはとても面白いと思いました。店舗ごとにアミューズメント感・POPなどで、商品の魅力を引き出す取り組みに違いを出すことで、その地域に合わせたマーチャンダイジングが行われていることに魅力を感じました。情報マネジメントの重要性など、多角的に物事を捉える能力を身に付けさせたいと思いました。
6月6日(火)~7日(水)の2日間、道徳教育推進教師研修講座が開催されました。受講された先生方は、「道徳教育のコーディネーター」となるための視点と、「道徳科の授業、各教科等での道徳のアドバイザー」となるための視点について理解を深め、自校の特色を生かした道徳教育に向けた実践力を磨くことができました。
2日目の午前は、十文字学園女子大学 教授 浅見 哲也氏による御講義が行われました。豊富な事例を基に道徳教育全体について御教授いただき、道徳教育の推進における大切なポイントを学ぶことができました。
【受講者の感想】
・道徳教育推進教師としてどんなことに取り組めばよいのか迷い悩んでいましたが、受講後は、道徳教育や道徳科の大切さを改めて実感し、学校全体として取り組みたいこと、授業で取り組みたいことが明確になりました。
・浅見先生からは、「全教育活動を通じて行う道徳教育」と「道徳教育の要となる道徳科の授業」についてなど、自分自身の中で曖昧だった部分等を分かりやすくお話ししていただきました。学校の教育活動は道徳教育に関わるものばかりであり、それを道徳推進教師が中心となり「意識し、つなげる」ことが大切であることを学びました。
・演習では道徳教育推進教師としてどんなアプローチができるのかを考えることができました。 また同じグループの先生方も同じように悩んでいることを聞いてほっとしたところもあります。アドバイスもたくさんもらえて、充実した演習になりました。
6月6日(火),7日(水)の2日間,標記講座を開催し,4名の受講者が参加されました。
この講座は,観察,実験や演習を通して,理科を指導する小学校教員としての指導力の向上と授業改善への意欲を高めることをねらいとして開催しました。
理科の授業改善についての講義,観察,実験の工夫,プログラミング学習等幅広い内容を取り上げ,理科を指導する教員としての実践力向上を図る内容としました。
日程と内容は,以下のとおりです。
【1日目】午前:講義「理科の授業改善の視点」
講義・実験「観察,実験の工夫~A物質・エネルギー~」
午後:講義・実験「観察,実験の工夫~A物質・エネルギー~」
講義・実験「問題解決の力を育む観察,実験」
【2日目】午前:講義・実験「観察,実験の工夫~B生命・地球~」
午後:講義・実験「理科におけるプログラミング学習」
【受講した先生方の感想】
・担当したことのない学年の授業の見通しや実験道具について学ぶことができたので
ありがたかった。十二分に目標が達成できた素晴らしい講座だった。
・児童の気分で参加でき、こんな進め方をすれば主体的にできるということが分かっ
た。理科の領域をまんべんなく指導していただき、とても役立った。
・子供たちが楽しく学べる内容だった。教材開発の大切さや主体的な学びにつながる
授業展開の方法など多くのことを学ぶことができた。プログラミングは苦手分野だ
ったが、ゆっくり進めてくださったので楽しく学習できた。大満足の2日間だっ
た。せっかくの学びをこの場だけにせず、どんどん子供たちに還元していきたい。
・理科が苦手だったが、どの分野も感動してしまう現象を生で見ることができたり、
楽しい体験をしたりすることができた。こんなに楽しいのなら、クラスの子供たち
はもっと喜んで学習に取り組むだろうと実感した。理科嫌いだった私が、理科が少
し好きになれた。
6月6日(火)標記講座を開催しました。
小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の特別支援教育コーディネーターの先生方34名が受講され、午前は「特別支援教育コーディネーターの役割」について学びました。午後は、中学校の先生からの実践発表があり、具体的な取組について紹介していただきました。その後、グループに分かれて、特別支援教育コーディネーターとしての「事例検討の進め方」について演習を行いました。


【受講者の感想】
・校内での動画研修、地域若者サポートステーションなどの保護者への情報提供等、すぐに校内で情報共有したいことがたくさんありました。「事例検討の進め方」についても、KPT法や話し合った内容など参考になりました。
・これまで特別支援教育コーディネーターという立場でケース会議等の計画、運営等の経験はありませんでした。具体的には、会議のゴールを設定し、それに向けてどのように取り組んでいくのか、大変参考になりました。
・ケース会議に出席したことは何度もあるが、主催することを考えると、難しかったです。短時間で実りのある会議にするための工夫を考えることができたし、他の先生方の工夫も参考になりました。また、特別支援学校の先生の視点やアドバイスも大変参考になりました。
6月2日(金)標記講座を開催しました。小・中・高・特別支援の8名(聴講含む)の先生方が受講され、Chromebookの基本操作、電子黒板への接続、授業に活用できる各種アプリの演習を行いました。
【講座の内容】
Chromebookについて
Chromebookの基本操作
電子黒板の活用
授業への活用
【講座の様子】


【受講者の感想】
・Chromebookを使うことで時間が足りなくなることがあったので、教師も児童もこの少しの時間の短縮により、同じ時間でもより意味のある内容になると感じました。
・Chromebookの特徴や他のタブレットとの比較が参考になりました。当たり前のようにこれまで使用していましたが、Chromebookの特徴を知ることができたので、学校に戻った時の実践が楽しみになりました。