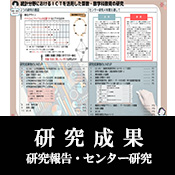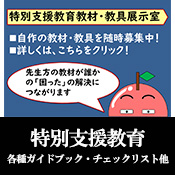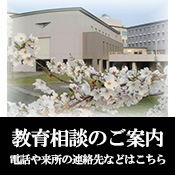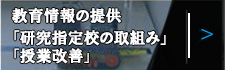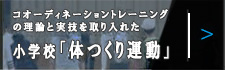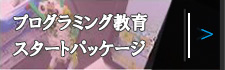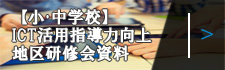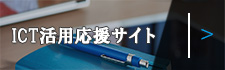新着情報
6月17日(火)、18日(水)、標記講座を開催し、特別支援学校、県立高校の先生方が受講されました。講義・演習を踏まえて、資料とクラウドを活用した学習活動を考えてもらい、考えた内容の発表・協議を通して、学習過程を踏まえた学習者中心の授業づくりについての理解を深めることができました。
【講座の内容】1日目 講 義 歴史資料から考える青森市の歴史 講師 青森市民図書館歴史資料室 室長 工藤 大輔 講義・演習 地理院地図を活用した地理教育の実践 講師 国土地理院東北地方測量部 次長 清水 乙彦 講義・演習 資料を活用した授業の充実に向けて
2日目 演習・協議 社会的な見方・考え方が働く教材づくり
【受講者の感想】・生徒に地元地域の歴史に興味をもってほしいという思いがあるため、改めて青森県や勤務校のある八戸市の年表を整理して、地域の歴史の転換点になるような大きな出来事をピックアップしたいと考えた。・授業においても、問いの追求にどんな資料が必要か、その資料は適切かを考えながら準備をすすめていきたいと思...
6月17日(火)標記講座を開催しました。15名の先生方が受講されました。 午前の前半では、UD(ユニバーサルデザイン)を取り入れた授業づくりや授業改善の視点について、講義と演習を行いました。午前の後半には、「私の授業改善の取組」と題して、つがる市立向陽小学校の吉村聡子先生に実践発表をしていただきました。単元のゴールを見据えた1時間の授業の組み立て方や、授業外に児童が英語に触れる工夫など、素晴らしい実践を御紹介いただきました。
午後は、上智大学短期大学部の狩野晶子教授によるワークショップ形式の講義を行っていただきました。講義を通して受講者の先生方が児童の気持ちになって考えることで、納得感をもってお話を聞くことができたと感じています。UDの視点から英語での指示の出し方や活動のポイントなどを教えていただき、明日からの実践にすぐに役立つ内容ばかりでした。「もっとお話を聞きたい」という声が上がるほど、充実した3時間となりました。
【講座の内容】・講義・演習 外国語・外国語活動の授業づくりと授業改善の視点 青森県総合学校教育センター 指導主事 長谷川 紘一・発表 私の授業改善の取組...
6月17、18日に中学校理科実験講座が開催されました。受講された先生方は14名となり、活気あふれた講座となりました。日程は以下の通りです。 6月17日(火)午前:講義「理科授業改善の視点」 午後:講義・実験「授業で使える観察・実験の工夫」(3学年2分野の内容) 6月18日(水)午前:講義・実験「授業で使える観察・実験の工夫」(2学年1分野の内容) 午後:講義・実験「授業で使える観察・実験の工夫」(1学年2分野の内容)
今年度は、細胞分裂と花粉管の観察、金星と月の模型作り、マグネシウムの燃焼、酸化銅の還元、電気回路カードづくり、動物の分類、火山灰の観察、火成岩と堆積岩の分類の観察、実験を行いました。【講座の様子】
6月17日(火)、上記の講座が開催されました。受講者は小学校8名、中学校4名、高等学校3名、特別支援学校8名、聴講者1名、合計24名でした。特別支援学校フォローアップ研修講座(前期)と合同開催で行われました。
北川准教授の講義・演習では、自立活動の基本的事項や個別の指導計画の作成と評価をどのように考えていけばよいのか等について、事例を交えながらお話いただき、動画を見て対象児童の実態を捉え、課題(指導すべき大切なポイント)を導き出す演習を行いました。午後の演習では、担当する幼児児童生徒の実態から、どのように目標設定をしたか、その理由を自分なりに再考したりまとめたりする機会としました。
【研修内容】
講義・演習「自立活動の指導の基本的理解」(講師:文教大学 准教授 北川 貴章氏)
演習「障がいのある幼児児童生徒の実態把握と目標設定」
【受講者の感想】
・自立活動の基本的な考え方から、これからどのように自立活動を行っていけばよいのかといった実践的なことまで、知りたいなと思っていたことを丁寧に学ばせていただいたと感じている。児童の実態を捉えるのも自分の主観が含まれること...
6月3日(火)標記講座を開催しました。小・中・高校から3名の先生方が受講され、Chromebookの基本操作、電子黒板との接続に関する演習を行いました。
【講座の内容】
Chromebookの基本操作
電子黒板との接続
【受講者の様子】
【受講者の感想】
・Chromebookの基本操作を丁寧に分かりやすく教えていただき、ありがとうございました。授業における活用の仕方等、知りたいことや身に付けたいことがもっとあるので、また研修会に参加させていただきたいと思います。
・とても丁寧に教えて頂き、大変勉強になりました。ありがとうございました。来年は他の講座にも参加してみたいと思います。
・受講目的は概ね達成されたと思ます。Chromebookの基本的な操作や特徴を実際に体験することができたのでよかったです。
6月3日(火)~4日(水)の2日間、道徳教育推進教師研修講座が開催されました。受講された先生方は、「道徳教育のコーディネーター」となるための視点と、「道徳科の授業や各教科等での道徳のアドバイザー」となるための視点について理解を深め、自校の特色を生かした道徳教育に向けた実践力を磨くことができました。
2日目の午前は、十文字学園女子大学 教授 浅見哲也氏による御講義が行われました。豊富な事例を基に道徳教育の推進について、また、模擬授業を通して道徳科の授業づくりについて御教授いただき、道徳教育の推進における大切なポイントを学ぶことができました。
【講座の内容】
1日目
・講義「道徳教育推進教師の役割と取組~コーディネーター・アドバイザーとして~」
・発表「我が校の道徳教育~学校全体で取り組む道徳教育の実際~」
(発表者)平川市立猿賀小学校 教諭 佐藤 牧子
外ヶ浜町立蟹田中学校 教諭 篠原 千代子
・講義「自校の特色を生かした道徳教育展開プランづくり」
2日目
・講義「学校の特色を生かした道徳教育~道徳教育をマネジメントする~」
(講師)十文字学園女子大学 教授 浅見 哲也
・演...
6月2日(月),3日(火)に標記講座が開催され,県内の小学校・中学校・特別支援学校から18名の先生方が参加しました。
【講座の内容】
6月2日(月)
1.講義 「総合的な学習の時間の役割」
2.講話 「地域再生×教育×農業振興×エンタメ
『この街で夢をかなえる』~地域活性化アイドル達の挑戦~」
有限会社 リンゴミュージック 代表取締役 樋川 新一
3.演習・協議「探究的な学習の過程で学ぶ総合的な学習の時間」
4.発表 「探究的に学ぶ総合的な学習の時間の実践」
6月3日(火)
1.講義 「探究的な学習の過程で取り組む総合的な学習の時間」
山形大学学術研究院 教授 野口 徹
2.演習・協議「探究的な学習の過程で学ぶ総合的な学習の時間」
【受講者の様子】
5/27(火)に標記講座が開催されました。小学校、中学校、高等学校、特別支援学校合わせて77名の先生方が受講されました。
【講座の内容】
「学年主任の役割とは」の講義では、各校種別に分かれて学年主任の職務について研修を行いました。高等学校部会では、青森県立青森高等学校の大里智子先生をお招きして、ご自身の経験を踏まえながら学年主任の職務について伝えていただきました。
「組織経営とミドルリーダー」の講義では、日本大学文理学部教授の藤平敦先生をお招きし、危機管理を含めた学年主任のミドルリーダーとしての役割について、ご講話いただきました。受講者同士の協議では、自校での教育活動をイメージしながら、熱心に意見交流を行う先生方の姿が印象的でした。
【受講者アンケートから】
・教員と保護者の対等な関係を意識し、共に生徒を育てるという思いを共有することの重要性を感じました。
・早速、学年会議の中で、「気になる生徒」「問題行動」のマイナスだけでなく、「輝く生徒」など「良い所探し」を提案し、前向きな目を鍛えられる学年経営をしたいと思います。
・マネジメントの視点で学年経営を行う手法として、生徒や学年団の行動を...
{{item.Topic.display_publish_start}}