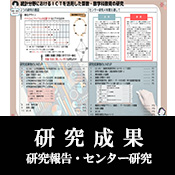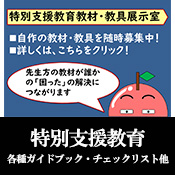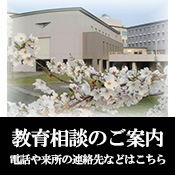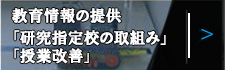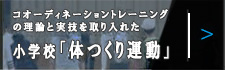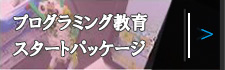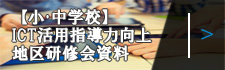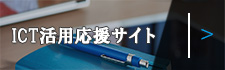新着情報
6月30日(月)標記講座を開催し、9名の先生方が受講されました。
午前は、青森県の課題をもとにして、問題発見・解決の過程を重視した授業作りについて講義・演習を行いました。午後は、弘前大学の田中義久教授に「数学的な見方・考え方を働かせる授業」について講義・演習を行っていただきました。演習を通して様々な課題や題材に取り組み、数学的な資質や能力、見方や考え方について学びを深める充実した時間となりました。
【講座の内容】
・講義・演習 問題発見・解決の過程を重視した学習の授業改善
青森県総合学校教育センター 指導主事 石塚 香織
・講義・演習 数学的な見方・考え方を働かせる授業
弘前大学教育学部 教授 田中 義久
7月3日(木)、4日(金)の2日間、標記講座を開催しました。
【講座の内容】
(1日目 所内)
■講義:「指導と評価の一体化」について
■講義:高等学校における農業教育について
講師:県立名久井農業高等学校 校長 小笠原理高 氏
■講義:県産農産物の輸出促進に向けた県の取組について
講師:県観光交流推進部県産品販売・輸出促進課 輸出促進グループ
総括主幹 本田斉与 氏
■演習:ICTを活用した教科指導の実践
(2日目 所外 県産業技術センター・農業協同組合)
■講義・演習:国内における輸出米事業の取組と目指すべき経営展開
講師:株式会社クボタ アグリ生販推進部新規事業推進室 米輸出事業推進課
佐藤 樹 氏
■講義・視察:県産果樹におけるブランド化と販路拡大(海外)の取組
講師:JAつがる弘前 りんご販売部販売課
課長 出雲正人 氏
7月1日(火)、2日(水)に高等学校外国語科言語活動実践講座を開催しました。参加者は生徒役となって様々な言語活動を直接体験し、それを踏まえて授業デザインについて演習・協議を行いました。活動の順序やファシリテーションの工夫など、授業を構成する上での重要な視点を共有し、受講者一人ひとりにとって学びの多い研修となったように思われます。
【講義内容】 1日目:「生徒の英語運用能力を育成する言語活動」 講師:県立八戸高等学校 教諭 當麻 進仁 2日目:「効果的・実践的な言語活動の実現に向けて」
【講座の様子】
【受講者からの感想】
〇自身の担当する科目での言語活動の実践方法を考え、実際に活動を組み立てながら生徒の動きを想像することができた。今まで実践したことがない言語活動の展開順で計画し、生徒が不安なく活動できるようにするために、どのような手立てと指導の工夫をできるか深く考えることができた。
〇生徒の立場で言語活動を体験することで、単元の内容をより深く学ぶことができたと思います。初めは慣れない生徒達も経験を重ねることで、学習意欲や知識の定着につながっていくと感じました。
7月1日(火)C22 時間的・空間的な関係を探究する理科野外実習講座[地学]を鯵ヶ沢町(七里長浜周辺)及びつがる市(出来島最終氷河期埋没林、亀ヶ岡石器時代遺跡、縄文住居展示館)の研修地で開催しました。七里長浜では、海成段丘(第四紀後半以降の約10万年周期で繰り返される気候変化、それに伴う高さ100m以上の海面変化、これらと局地的な地殻変動の重ね合わせにより形成された)の形成過程や海岸地形(海食崖、海食洞、ノッチ、ベンチ)等について観察しました。出来島最終氷河期埋没林の露頭では約2万8千年前の地層から発見された埋没林(エゾマツやアカエゾマツ等の針葉樹)を観察しました。最終氷期後期(約8万~2万年前)の極寒期に洪水などの急激な環境の変化によって針葉樹が水没し、その根が水分により、真空パックされたため腐らずに残ったものと考えられてる。
亀ヶ岡石器時代遺跡及び縄文住居展示館では、つがる市の学芸員の解説がありました。定住成熟期後半の大規模な共同墓地であり、高度な精神文化を示すとともに、内湾地域の汽水地域における生業及び高い精神性による祭祀・儀礼の在り方を示す重要な遺跡であることが分かりました。受講された先...
6月17日(火)、18日(水)、標記講座を開催し、特別支援学校、県立高校の先生方が受講されました。講義・演習を踏まえて、資料とクラウドを活用した学習活動を考えてもらい、考えた内容の発表・協議を通して、学習過程を踏まえた学習者中心の授業づくりについての理解を深めることができました。
【講座の内容】1日目 講 義 歴史資料から考える青森市の歴史 講師 青森市民図書館歴史資料室 室長 工藤 大輔 講義・演習 地理院地図を活用した地理教育の実践 講師 国土地理院東北地方測量部 次長 清水 乙彦 講義・演習 資料を活用した授業の充実に向けて
2日目 演習・協議 社会的な見方・考え方が働く教材づくり
【受講者の感想】・生徒に地元地域の歴史に興味をもってほしいという思いがあるため、改めて青森県や勤務校のある八戸市の年表を整理して、地域の歴史の転換点になるような大きな出来事をピックアップしたいと考えた。・授業においても、問いの追求にどんな資料が必要か、その資料は適切かを考えながら準備をすすめていきたいと思...
6月17日(火)標記講座を開催しました。15名の先生方が受講されました。 午前の前半では、UD(ユニバーサルデザイン)を取り入れた授業づくりや授業改善の視点について、講義と演習を行いました。午前の後半には、「私の授業改善の取組」と題して、つがる市立向陽小学校の吉村聡子先生に実践発表をしていただきました。単元のゴールを見据えた1時間の授業の組み立て方や、授業外に児童が英語に触れる工夫など、素晴らしい実践を御紹介いただきました。
午後は、上智大学短期大学部の狩野晶子教授によるワークショップ形式の講義を行っていただきました。講義を通して受講者の先生方が児童の気持ちになって考えることで、納得感をもってお話を聞くことができたと感じています。UDの視点から英語での指示の出し方や活動のポイントなどを教えていただき、明日からの実践にすぐに役立つ内容ばかりでした。「もっとお話を聞きたい」という声が上がるほど、充実した3時間となりました。
【講座の内容】・講義・演習 外国語・外国語活動の授業づくりと授業改善の視点 青森県総合学校教育センター 指導主事 長谷川 紘一・発表 私の授業改善の取組...
6月17、18日に中学校理科実験講座が開催されました。受講された先生方は14名となり、活気あふれた講座となりました。日程は以下の通りです。 6月17日(火)午前:講義「理科授業改善の視点」 午後:講義・実験「授業で使える観察・実験の工夫」(3学年2分野の内容) 6月18日(水)午前:講義・実験「授業で使える観察・実験の工夫」(2学年1分野の内容) 午後:講義・実験「授業で使える観察・実験の工夫」(1学年2分野の内容)
今年度は、細胞分裂と花粉管の観察、金星と月の模型作り、マグネシウムの燃焼、酸化銅の還元、電気回路カードづくり、動物の分類、火山灰の観察、火成岩と堆積岩の分類の観察、実験を行いました。【講座の様子】
6月17日(火)、上記の講座が開催されました。受講者は小学校8名、中学校4名、高等学校3名、特別支援学校8名、聴講者1名、合計24名でした。特別支援学校フォローアップ研修講座(前期)と合同開催で行われました。
北川准教授の講義・演習では、自立活動の基本的事項や個別の指導計画の作成と評価をどのように考えていけばよいのか等について、事例を交えながらお話いただき、動画を見て対象児童の実態を捉え、課題(指導すべき大切なポイント)を導き出す演習を行いました。午後の演習では、担当する幼児児童生徒の実態から、どのように目標設定をしたか、その理由を自分なりに再考したりまとめたりする機会としました。
【研修内容】
講義・演習「自立活動の指導の基本的理解」(講師:文教大学 准教授 北川 貴章氏)
演習「障がいのある幼児児童生徒の実態把握と目標設定」
【受講者の感想】
・自立活動の基本的な考え方から、これからどのように自立活動を行っていけばよいのかといった実践的なことまで、知りたいなと思っていたことを丁寧に学ばせていただいたと感じている。児童の実態を捉えるのも自分の主観が含まれること...
6月3日(火)標記講座を開催しました。小・中・高校から3名の先生方が受講され、Chromebookの基本操作、電子黒板との接続に関する演習を行いました。
【講座の内容】
Chromebookの基本操作
電子黒板との接続
【受講者の様子】
【受講者の感想】
・Chromebookの基本操作を丁寧に分かりやすく教えていただき、ありがとうございました。授業における活用の仕方等、知りたいことや身に付けたいことがもっとあるので、また研修会に参加させていただきたいと思います。
・とても丁寧に教えて頂き、大変勉強になりました。ありがとうございました。来年は他の講座にも参加してみたいと思います。
・受講目的は概ね達成されたと思ます。Chromebookの基本的な操作や特徴を実際に体験することができたのでよかったです。
6月3日(火)~4日(水)の2日間、道徳教育推進教師研修講座が開催されました。受講された先生方は、「道徳教育のコーディネーター」となるための視点と、「道徳科の授業や各教科等での道徳のアドバイザー」となるための視点について理解を深め、自校の特色を生かした道徳教育に向けた実践力を磨くことができました。
2日目の午前は、十文字学園女子大学 教授 浅見哲也氏による御講義が行われました。豊富な事例を基に道徳教育の推進について、また、模擬授業を通して道徳科の授業づくりについて御教授いただき、道徳教育の推進における大切なポイントを学ぶことができました。
【講座の内容】
1日目
・講義「道徳教育推進教師の役割と取組~コーディネーター・アドバイザーとして~」
・発表「我が校の道徳教育~学校全体で取り組む道徳教育の実際~」
(発表者)平川市立猿賀小学校 教諭 佐藤 牧子
外ヶ浜町立蟹田中学校 教諭 篠原 千代子
・講義「自校の特色を生かした道徳教育展開プランづくり」
2日目
・講義「学校の特色を生かした道徳教育~道徳教育をマネジメントする~」
(講師)十文字学園女子大学 教授 浅見 哲也
・演...
6月2日(月),3日(火)に標記講座が開催され,県内の小学校・中学校・特別支援学校から18名の先生方が参加しました。
【講座の内容】
6月2日(月)
1.講義 「総合的な学習の時間の役割」
2.講話 「地域再生×教育×農業振興×エンタメ
『この街で夢をかなえる』~地域活性化アイドル達の挑戦~」
有限会社 リンゴミュージック 代表取締役 樋川 新一
3.演習・協議「探究的な学習の過程で学ぶ総合的な学習の時間」
4.発表 「探究的に学ぶ総合的な学習の時間の実践」
6月3日(火)
1.講義 「探究的な学習の過程で取り組む総合的な学習の時間」
山形大学学術研究院 教授 野口 徹
2.演習・協議「探究的な学習の過程で学ぶ総合的な学習の時間」
【受講者の様子】
5/27(火)に標記講座が開催されました。小学校、中学校、高等学校、特別支援学校合わせて77名の先生方が受講されました。
【講座の内容】
「学年主任の役割とは」の講義では、各校種別に分かれて学年主任の職務について研修を行いました。高等学校部会では、青森県立青森高等学校の大里智子先生をお招きして、ご自身の経験を踏まえながら学年主任の職務について伝えていただきました。
「組織経営とミドルリーダー」の講義では、日本大学文理学部教授の藤平敦先生をお招きし、危機管理を含めた学年主任のミドルリーダーとしての役割について、ご講話いただきました。受講者同士の協議では、自校での教育活動をイメージしながら、熱心に意見交流を行う先生方の姿が印象的でした。
【受講者アンケートから】
・教員と保護者の対等な関係を意識し、共に生徒を育てるという思いを共有することの重要性を感じました。
・早速、学年会議の中で、「気になる生徒」「問題行動」のマイナスだけでなく、「輝く生徒」など「良い所探し」を提案し、前向きな目を鍛えられる学年経営をしたいと思います。
・マネジメントの視点で学年経営を行う手法として、生徒や学年団の行動を...
5月16日(金)標記講座を開催しました。受講者は小学校8名、中学校6名、高等学校8名、特別支援学校8名、聴講者6名、合計36名でした。
午前の講義は、はじめに「いじめについての認識と理解」と題し、県教育庁学校教育課の斗沢慎一郎指導主事による講義を行いました。
次に「いじめの理解といじめ防止のための取組~いじめ問題の現状と課題~」というテーマで、上越教育大学大学院の高橋知己教授が講義・演習を行いました。さらに、午後も「いじめの理解といじめ防止のための取組~未然防止・早期発見の方法、アンケートの工夫~」というテーマでの高橋教授の講義・演習が行われました。
講義では、高橋教授がこれまで関わった様々ないじめ案件や重大事案の実際について、多くの事案の第三者委員を務めた経験から言える現場の先生方の取るべき対応や準備すべき資料、心構え、校内組織体制の在り方等を力強くご講義下さり大変多くの知識、手立てや考え方等を学ぶことができました。また、いじめと不登校は切り離せない問題として、これまでの膨大なアンケート調査の分析を通して明らかになった様々な実態、諸課題についてもお聞か...
5月14日(水)に教務主任研修講座を開催しました。小学校29名、中学校29名、高等学校11名、特別支援学校7名の計76名の先生方が参加され、講義や協議を通して、学校運営を円滑かつ適切に推進する教務主任の職務や役割についての理解を深めました。
【内容】
講義「教務主任に期待する」[講師:下山 敦史 学校教育課長]
講義「『カリキュラム・マネジメント』の充実に向けて」[講師:若松 大輔 先生(弘前大学教職大学院助教)]
講義・協議「教務主任の職務と役割」
[小学校部会講師・助言者:三浦 匠 先生(大間町立奥戸小学校教頭)]
[中学校部会講師・助言者:森山 高志 先生(新郷村立新郷中学校教頭)]
[高等学校部会講師・助言者:鈴木 勝 先生(県立五所川原高等学校教頭)]
[特別支援学校部会講師・助言者:上村 愛輝子 先生(県立浪岡養護学校教頭)]
☀5/7(水) B02 教頭研修講座(前期)が開催されました。
小学校32名、中学校31名、高等学校14名、特別支援学校5名の合計82名が受講しました。受講された教頭先生方は教頭の教育活動、教職員のメンタルヘルス、教育現場におけるコーチングコミュニケーション、教頭の職務と役割について理解を深め、教頭として識見を高めることができました。
【研修内容】
「教頭の教育活動」:県教育庁教職員課
「教職員のメンタルヘルス」:青森県公認心理士・臨床心理士協会 事務局長 相馬 香里
「教育現場におけるコーチングコミュニケーション」:別府大学 客員教授 佐藤 敬子
「教頭の職務と役割」:県立五所川原工科高等学校 教頭 川崎 淳平
義務教育課長、特別支援教育課長
【講座の様子】
4月25日(金)にセンター広報誌「センターだより」第81号を発行いたしました。こちらからご覧ください。
4月24日(木)に「B07生徒指導主任・主事研修講座」が開催されました。
小学校21名、中学校15名、高等学校8名、特別支援学校6名の先生方が受講されました。生徒指導主任・主事として日常的に意識すべき校内外での動きや、喫緊の課題であるいじめや不登校の対応、そしてチーム学校としての連携のあり方について、講義や協議、意見交換を通して理解を深めました。
【研修内容】
・講義「生徒指導主任・主事の役割と生徒指導上の諸課題への対応」
・協議「生徒指導主任・主事として」
・講義「県内の生徒指導上の諸課題について」
県教育庁学校教育課生徒指導支援グループ 副参事 後村 敏明
・講義「不登校・いじめを生まない魅力ある学校づくりを目指して」(オンライン)
岡山県教育委員会 人権教育・生徒指導課 課長 髙橋 典久
3月7日(金)にセンター広報誌「センターだより」第80号を発行いたしました。こちらからご覧ください。
2年目研究員の研究論文がWebアップされました。こちらからご覧いただければと思います。
12月13日(金)にセンター広報誌「センターだより」第79号を発行いたしました。こちらからご覧ください。
9月24日(火)、25日(水)の2日間、標記講座を開催しました。プログラミング教育と環境構築やライブラリとWebAPIの活用、事象のモデル化とシミュレーションなどについて学びました。
【講座の内容】・プログラミング教育と環境構築・応用的プログラム・ライブラリとWebAPIの活用・事象のモデル化とシミュレーション
【講座の様子】
【受講者の感想】
・高等学校プログラミング基礎講座を受講し、Pythonプログラミングをはじめ、アルゴロジックや指示テスト、Geminiなど私にとって新たな発見でした。複数のデータを収集し、分析を行うプログラムを作成することができ、大変満足しています。まだまだ理解が浅い部分があり、今後さらに深めていきたいと考えています。ありがとうございました。
・受講目的は達成することができたと思います。私自身、これまでPythonに触れたことがなかったので、大変勉強になりました。
11月18日(月)、19日(火)の2日間、標記講座を開催しました。データベースの演習やプログラミングによるデータの活用と分析などについて学びました。
【講座の内容】・情報科の指導と評価について・データベースとSQL・表計算ソフトによるデータの活用と分析・プログラミングによるデータの活用と分析
【講座の様子】
【受講者の感想】
・データベースの実習、テキストマイニング、データ分析などの課題について、無理なく授業に展開できそうな感じでしたので今後実施したいと思います。すでに終えた単元については、来年度に活かせるように教材の準備をしていきます。特にデータ分析については、よい事例を教えていただきました。
・情報の分野では教員の専門性が重要となり、新しい技術や教育方法に関する研修を定期的に行い、自身が最新の情報を学び続ける意識を持ち続けていきたいと強く思いました。講座を通して得られた豊富なツールやアイディアを授業の実践に生かしていきたいと思います。ありがとうございました。
10月28日(月)、29日(火)の2日間、標記講座を開催しました。小学校・中学校・特別支援学校の21名の先生方が受講されました。「特別の教科 道徳」の授業改善に向けて、基本となる考え方や様々な手法について、講義や演習、協議を通して学びました。
【講座の内容】
1日目
・講義「考え、議論する道徳」の実現に向けて
・講義・演習「考え、議論する道徳」の授業づくり
・講義「特別の教科 道徳」の教材研究と授業構想
(講師)秋田公立美術大学 副学長 毛内 嘉威
2日目
・講義・演習「特別の教科 道徳」の授業改善とICT活用
・発表「考え、議論する道徳」の授業実践
(発表者)十和田市立四和小学校 教諭 黒滝 誠人
むつ市立大平中学校 教諭 菩提寺 学
【講座の予定】
10月5日(火)にセンター広報誌「センターだより」第78号を発行いたしました。こちらからご覧ください。
10月24日(木)標記講座を開催しました。12名の先生方が受講されました。
午前は、「主体的・対話的で深い学び」につながる単元構想や各活動の設定、ICTの活用についてお話をしました。また、講義の後半では、話すこと【やり取り】のMicro-Teachingを行い、体験的に学べる機会も設けました。
午後は、信州大学学術研究院の酒井 英樹教授に講義をしていただきました。同じ教科書を使用する先生方で班になり単元構想計画案を作成したり、CAN-DOリストについての理解を深めたりすることができました。受講者の質問にも答えていただき、充実した3時間となりました。
【講座の内容】・言語活動が主体となる授業づくりとICTの活用 青森県総合学校教育センター 指導主事 長谷川 紘一
・子どもの資質・能力を高める授業づくり 信州大学学術研究院 教授 酒井 英樹
【講座の様子】
10月9日(水)に通常の学級のユニバーサルデザイン研修講座を開催いたしました。 今年度は小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の先生方63名が受講されました。
早稲田大学大学院 教授 髙橋 あつ子 先生を講師に迎え、「通常の学級における学びのユニバーサルデザイン~学びの多様性に応える授業づくり~」というテーマで、演習を交えながらご講義いただきました。児童生徒の多様な学びを保障するUDLの考え方やUDLの視点を取り入れた授業づくりについて、事例の紹介や演習を交えながら分かりやすくお話していただきました。 またその後、中学校の先生による実践発表と協議を行いました。講座を通して、これまでの自身の授業を振り返るとともに、明日からの実践に生かしたいと大変好評でした。
10月8日(火)に県立学校臨時講師等研修講座Ⅱを実施しました。7名が受講し、午前は「教職員の服務規律について」と「情報セキュリティについて」を、午後は「生徒理解について」を実施し、その後高等学校の先生方は「教科指導」について、特別支援学校の先生方は「特別支援教育の基礎・基本」について学びました。それぞれの講義・演習を通して教員として必要な基礎知識を再確認し、理解を深めていた様子でした。
【受講者の感想】
・教壇に立つ者として必要となる知識や技能を習得し、使命感を強く持とうと思った。
・教職員の服務規律についての講座を受け、改めて気をつけて日々を過ごそうと思いました。管理職への報告は漏らさずに行おうと思いました。
・児童生徒との関わりを医療的な観点と併せて、教育的観点で行う大切さや必要性を学び、担任教諭と共に児童生徒の将来を支えて行きたい。
・実際に起きた例を挙げた説明により、情報セキュリティや生徒への理解が深まった。教科指導では、教科の特徴と評価方法、教材研究といった基本的なことから、勤務中の時間の使い方等をご教授いただいた。
9月30日(月)、「気になる子供」のかかわり方研修講座(中・高等学校)が開催されました。受講者は中学校17名、高等学校26名、特別支援学校8名、研究員2名、聴講者2名、合計55名でした。1日を通じて「気になる子供」の視点でかかわり方を見直す講義・演習が行われ、生活面・学習面で困り感のある子供への支援方法、また、発達障害の基本的な理解を深め、子供へのかかわり方を見直し、アセスメントの実際とチーム支援の在り方を確認できる機会となりました。講義の間には多くの演習の時間も設けられ、より具体的なかかわり方の方法を学んだり、実際の事例から考えを深めたりしました。
【研修内容】講義・演習「気になる子供」の視点でかかわり方を見直す 弘前医療福祉大学 教授 小玉 有子
10月4日に標記講座を開催しました。 午前は、青森中央短期大学附属第一幼稚園様で保育参観を行いました。 午後は、東海大学児童教育学部の寳來生志子准教授をお招きし、幼保小の架け橋プログラムについて、「みんなで伴走し、育てよう!青森の子どもたち~架け橋期の教育を考える~」と題してご講義いただき、その後、保育参観をもとに、園児の学びの姿について協議しました。保育者と小学校教員とが、幼児教育と小学校教育の学びのつながりについて理解を深める、貴重な機会となりました。【講座の内容】 ・保育参観~保育活動の実際~ 青森中央短期大学附属第一幼稚園
・講義、演習 幼保小の架け橋プログラムについて
「みんなで伴走し、育てよう!青森の子どもたち~架け橋期の教育を考える~」
講師 東海大学 児童教育学部
准教授 寳來 生志子 氏
9月25日(水)標記講座を開催しました。11名の先生方が受講されました。
午前は、県立高校入試や県学習状況調査の結果を踏まえ、課題に対応するためにどのように授業改善していったらよいのかお話をさせていただきました。
午後は、文部科学省の入之内調査官に講義をしていただきました。全国の実践事例や小中連携、ALTの参画、MEXCBT(メクビット)の活用についてなど、多岐に渡ってお話をしてくださいました。今後、どのような方向で授業改善をしていけばよいのか具体が見え、実践意欲が高まったあっという間の3時間でした。
【講座の内容】・中学校英語における課題と授業改善の視点 青森県総合学校教育センター 指導主事 長谷川 紘一
・中学校英語教師に求められる役割 文部科学省初等中等教育局 教育課程課 外国語教育推進室 教科調査官 入之内 昌徳
【講座の様子】
9月24日(火)に小学校1名、中学校14名、高等学校10名、特別支援学校7名の計32名の先生方が参加され、標記の講座を開催しました。講師に筑波大学人間系の京免徹雄准教授をお迎えし、学びを人生に生かすためにキャリア教育が重要であることや、「キャリア・パスポート」を児童生徒との対話のツールとして活用していくことなど、講義していただきました。その後、演習・協議では、他校種のつながりを中心に明日からできることについての演習・協議を行いました。
【内容】
講義「いま、なぜキャリア教育なのか?~学校教育におけるキャリア教育の役割~」
筑波大学人間系 京免 徹雄 准教授
演習・協議「キャリア教育への取組」
県総合学校教育センター 指導主事6名
9月30日(月)にセンター広報誌「センターだより」第77号を発行いたしました。こちらからご覧ください。
9月17日(火)に標記研修講座を開催しました。 昨年度に引き続き、講師として東北学院大学文学部教授の稲垣忠氏をお招きし、講義・演習をしていただきました。稲垣教授による講義・演習では、「生徒が切実感をもって他者と伝え合う学び」や「ルーブリックで生徒の学びの質を保証する」など、探究的な学び、情報活用型プロジェクト学習に必要となる知見を数多く得られる構成となっており、学びの多い一日となりました。
■講義・演習「探究する学習のデザイン」 講義・演習「学習活動の設計と評価」 (講師)東北学院大学文学部 教授 稲垣 忠■協議「総合的な探究の時間の取組」 (助言者)県総合学校教育センター 高校教育課 指導主事 小関 央高 指導主事 青木 雅俊
【講座の様子】
9月4日(水)、標記講座を開催しました。参加者は小学校8名、中学校5名、高校2名の合計15名でした。 「養護教諭のスキルアップ」と題し、神奈川県立保健福祉大学 准教授 高橋 佐和子先生から、前半は専門性を活かした健康教育の進め方について、健康教育を行うためのヒントをたくさん教えていただき、高橋先生の実践もご紹介していただきました。後半は、養護教諭に求められる救急処置の知識と技術について、フィジカルアセスメントを具体的に教えていただいたり、グループワークにおいて養護教諭同士で事例を検討することにより、学びを深めることができました。また、スキルラダーを用いて、自分の実践を振り返り、成長を実感する機会となりました。
【研修内容】講義・演習「養護教諭のスキルアップ ~健康教育&救急処置~」 神奈川県立保健福祉大学 准教授 高橋 佐和子 氏
【講座の様子】
9月12、13日に標記講座を開催しました。1日目は、問いを大切にした授業づくりやICTの効果的な活用について講義・演習を行いました。2日目は、大妻女子大学澤井陽介教授をお招きし、午前は「主体的・対話的で深い学びの実現を目指す問題解決的な学習の在り方」と題してご講義いただき、午後は授業案作りの演習を行いました。子供たちの「問い」を大切にした授業改善について学びました。【講座の内容】 1日目 講義・演習 「主体的・対話的で深い学びの実現を目指す問題解決的な学習の授業改善」 「ICTの効果的な活用」 実践発表「思考力・判断力・表現力等を育てる社会科教育の実践」 2日目 講義・演習 「主体的・対話的で深い学びの実現を目指す問題解決的な学習の在り方」 講師 大妻女子大学 教授 澤井 陽介 氏
9月4日(水)、上記の講座が開催されました。受講者は小学校6名、中学校6名、高等学校1名、特別支援学校2名、聴講者1名、合計16名でした。後期は、中堅教諭等資質向上後期研修(特別支援学校)と一部合同開催で行われました。
午前の演習では、中堅教諭等資質向上後期研修(特別支援学校)の受講者による自立活動の実践を参観することを通し、実態把握から授業実践までのプロセスを学びました。午後の協議・演習では自身の自立活動の指導における課題を基に、協議を行いました。協議を通して自立活動の指導内容及び指導方法の多様な見方・考え方にふれ、自立活動の指導における課題解決のヒントを得る機会となったようです。
【研修内容】
演習「実態把握に基づく指導実践」(中堅教諭等資質向上後期研修(特別支援学校)と合同開催)
協議・演習「自立活動の課題解決に向けて」
8月23日(金)、上記の講座が開催されました。受講者は小学校17名、特別支援学校6名、聴講者9名、合計32名でした。「『気になる子供』の視点でかかわり方を見直す」というテーマで、講義・演習が行われました。
講義では、阿部教授の豊富な経験から得られた教育現場での様々な困り感、つまずきを抱えた子供たちの実態や特性が紹介されるとともに、その困り感を察知するための視点と具体的な手立てや支援の在り方等について詳しくお話いただきました。演習では、グループごとにSCT(文章完成法)から得られた情報から人物像を検討していく作業を体験したり、授業中に集中できない子供へのよりよいかかわり方や手立て等を話合ったりする活動を行いました。
【研修内容】
講義・演習「『気になる子供』の視点でかかわり方を見直す」
講師:星槎大学大学院 教授 阿部 利彦 氏
【受講者の感想から】
・まさに、今受け持ちの学級で困っていることの答えが、たくさん見つかったような気がした。「気になる子供」自身が一番困り感を抱えており、それを担任が理解し寄り添った指導をし続ければ、少しずつ改善...
8月28日(水)に標記研修講座を開催しました。 昨年度に引き続き、講師として東京学芸大学大学院教育学研究科教授の西村圭一氏をお招きし、講義・演習をしていただきました。西村教授による講義・演習では、「生徒を主語にした授業をデザインすることの必要性」や「これからの統計教育の在り方」など、今後の数学教育に必要となる知見が数多く得られる構成となっており、受講者の心に残る学びの多い1日となりました。
■講義・演習「数学科における探究的な学び」 講義・演習「統計教育の充実」 (講師)東京学芸大学大学院 教育学研究科 教授 西村 圭一■演習・協議「仮説検定の授業デザイン」 (講師)県総合学校教育センター 高校教育課 指導主事 小関 央高
8月27日(火)標記講座を開催しました。37名の先生方が受講されました。
午前は、学級活動(1)(2)(3)のポイントや実践事例、ICTの活用についてお話をさせていただきました。また、学級活動(2)の食育の授業づくりを班で体験していただきました。
午後は、帝京大学の安部教授に講義をしていただきました。特別活動の核となるお話や全国の豊富な事例をご紹介いただきました。また、班で学級活動(1)に関する日頃の悩みや課題を共有する時間もあり、充実した3時間となりました。
【講座の内容】・自主的・実践的な態度を育てる学級活動とICTの活用 青森県総合学校教育センター 指導主事 長谷川 紘一・生きる力の育成と特別活動の役割 帝京大学教育学部 教授 安部 恭子
【講座の様子】
8月27日(火)県立学校事務長研修講座(後期)が開催され、県立学校の事務長9名が受講しました。「学校施設の管理について」の講義を聴き、具体的な事例を参考にしながら今後の管理体制について考えを深めている様子でした。
【研修内容】
講義「学校施設の管理について」
(講師)県教育庁学校施設課
【研修の様子】
【受講者の感想】・具体的な例を出していただいたので、とても分かりやすく参考になりました。学校に戻ってから実践したいと思います。・貸付、使用許可等施設管理事務の中で本校にも該当する事があり、内容等確認でき、参考になりました。・建物の構造、また劣化がどのように進むのか分かった。・資料が今後の実務を行う上で、大変役立つもので、講座を受講出来てよかったです。
8月28日(水)に『特別支援教育におけるICT活用「基礎・基本」研修講座』を開催いたしました。 今年度は小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の先生方25名が受講、小学校、特別支援学校の先生方2名が聴講されました。
午前中は東北福祉大学教育学部 准教授 杉浦 徹 先生を講師に迎え、「特別支援教育におけるICT活用について~基本的な考え方と実践で大事にしたいこと~」という内容で講義・演習を行いました。子どもたちのできてうれしい気持ちを育てることの大切さについて、事例の紹介や多くの演習を交えながら分かりやすくお話していただきました。 午後は、特別支援学校の先生方2名の実践発表と、授業改善に向けた演習を行いました。これまでの自身の指導を振り返るとともに、これからの指導にどう生かすか、アイディアやヒントを見つけることができました。
令和6年7月27日(土)に、FR教育臨床研究所所長の花輪敏男氏をお招きして、センターセミナーⅠ「不登校児童生徒への支援」を開催いたしました。県内各地の市町村から、教育関係者だけでなく、一般の参加者も含めて55名の参加がありました。セミナーでは、学校・家庭・専門機関との連携の必要性、不登校児童生徒を自立に向けること、自主性を育むための具体的な言葉がけなどを示唆していただきました。セミナー後のアンケートからは、今後の不登校支援への実践について意欲的に書かれている内容が多く寄せられました。
【講座内容】 講義 「不登校児童生徒への支援」 講師 FR教育臨床研究所 所長 花輪 敏男 氏
【講座の様子】
8月21日(水)感性を育む音楽科実践講座が開催されました。前日からの鑑賞の学びを考える!小学校図工・音楽科講座と合同開催の講座であり、19名の先生方と校種・科目等をこえて鑑賞から広がるこれからの学びについての講義・演習、資質・能力を育む鑑賞の授業づくりについての協議・演習を行いました。
【研修内容】 1 講義・演習「感性を育むこれからの資質・能力」 講師 県総合学校教育センター 指導主事 道川 里奈 2 講義・演習「鑑賞から広がるこれからの学び」 講師 武蔵野音楽大学 准教授 山﨑 正彦 3 協議・演習「資質・能力を育む鑑賞の授業づくり」 助言者 武蔵野音楽大学 准教授 山﨑 正彦 県総合学校教育センター 指導主事 道川 里奈
{{item.Topic.display_publish_start}}