
9月3日(水)に標記講座を開催しました。「自立活動の授業実践の協議を通して、障がいによる学習上・生活上の困難を改善・克服を図るための専門性と実践的指導力の向上を図る。」ことを目的に実施いたしました。小学校2名、中学校3名、高等学校1名、特別支援学校4名、計10名の先生が参加されました。特別支援学校の中堅教諭等資質向上後期研修に参加している教師の事例を通して学び、自立活動の授業力の向上を図れるよう、インシデントプロセス法を用いて授業検討をおこないました。
【講義・演習内容】
午前 実態把握に基づく指導実践
午後 自立活動の課題解決に向けて
【講座の様子】

【受講者からの感想】
・これまで自立活動をしていましたが、担当している生徒の実態把握の大切さを改めて感じました。また、特別支援学校の先生方が実践されてる内容を聞くことができ、とても貴重な時間となりました。効果的なアプリや教材を現場の教科担任と共有して、実践してみたいと思いました。
・午後の自立活動の課題解決についての時間では、先生方から、いろんな角度からアドバイスを頂くことができ、生徒にとって効果的な支援方法を得ることができました。
・中堅教諭等資質向上後期研修に参加している先生の事例と午後の協議中、生徒の顔が思い出され、「あれができそう、これやってみたい」と構想が膨らみました。協議を通して自身の実践を振り返ることもできましたし、多様な見方・考え方に驚きの連続でした。この研修でたくさんのヒントをいただきました。後期の自立活動の時間をどう組み立てていくか楽しみになってきました。
9月30日(火)、標記講座を開催し、県内各地の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の32名の先生方が受講しました。講師には筑波大学の京免徹雄先生をお招きし、キャリア教育の在り方やキャリアパスポートの活用方法などについてご講義いただきました。また、講義を踏まえて、他校種の先生方と情報交換をしながら協議を行い、「縦の連携」を意識したキャリア教育の推進に向けて見通しを持つことができた様子でした。
【講座の内容】
講義「ウェルビーイングに向けた『ともに歩む』キャリア教育」
講師 筑波大学 准教授 京免 徹雄 氏
演習・協議「キャリア教育への取組」
【受講者の感想】
○今までの教育活動を振り返ると、キャリア教育を意識する場面はあまりなかったように思うが、講義を受ける中で、各教科の学びを繋げることや、教科と実生活を繋げること、またウェルビーイングのある学級経営等、日常の中で意識できることがたくさんあることに気付くことができた。また、キャリアパスポートは使い方次第でもっと有意義に活用できることもわかったので、今後の実践に生かしていきたい。
○子どもたちの将来にとって「キャリア教育」はとても大切だと思い、今までも様々な実践を積み重ねてきました。ただ、今回の講義を拝聴し、どういったキャリア教育を進めていけばいいのか、方向性が明確になった気がします。他者との関係と対話が未来志向を促進することや、学級のウェルビーイングを向上させることが個人のウェルビーイングの向上につながること、そして「語らせ、つなぎ、価値付け」を繰り返しながら対話や振り返りを続けることが大切だということなど、とても勉強になることばかりでした。今後の実践に活かしていきたいと思います。
○学校にキャリア教育全体計画があるものの、これまでしっかり読む時間がなかったので、今回の研修を通してその重要性を再認識した。そして、各教科の確かな学力も大事だが、生きていくための本当に必要な知識、学びを実生活につなげるのがキャリア教育の視点を持つことだと分かった。また、キャリア教育という漠然としたイメージに固執して、進路や就労に偏りすぎていたことに気付いた。普段の会話から毎日の授業、学校行事などその場その瞬間にキャリア教育は可能であり、生徒との対話から正しい意味付けやよりよい価値付けをしてあげることが大事であり、人生の物語の主人公は生徒自身であることを伝え、共に過ごす時間の伴走者になっていきたいと思った。
○子ども達と将来について考えるときに、どうしても現実的な部分や今の能力との比較をしてしまうことが多くあった。今回、京免先生の、「現実と折り合いをつけながら、進路探索を繰り返すことを経験した方が自分の進路を深く考えることができる」というお話を聞いて、日々の子どもたちとの会話の中で答えがでない、悩んでいる状態は悪いことではないのだと思うことができた。また、「困った友達を助けよう」、「励まそう」、「自分のことだけではなく相手のことを思って行動しよう」と日々子どもたちに伝えていることが、「自分の幸せだけでなく他の人、周囲の人の幸せあってこそのウェルビーイング」という考え方につながるのだと感じた。
9月26日(金)、「気になる子供」のかかわり方研修講座が開催されました受講者は中学校15名、高等学校20名、特別支援学校2名、聴講者5名、合計42名でした。様々な特性を持った子供たちが物事をどのように認識しているかについての理解や支援の方法、複数の視点でしっかりとアセスメントを行い、チーム支援につなげていくことなど、多くの具体例とともに学ぶことができました。
【研修内容】
講義「気になる子供」の視点でかかわり方を見直す
(講師)弘前医療福祉大学 教授 小玉 有子 氏
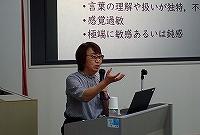
【受講者の感想から】
・小玉先生が多くの例をあげてくださり、これも最後に仰った「知ることから始まる」につながるのだと実感することができた。ご講義の中で、特性を持つ子供が、自分が上手くできないことをどう補うか、自分で解決できるようにする、というのはとても納得できた。
・小玉先生は講義の中で、アセスメントの重要性を強調されており、自分に不足している部分だと感じました。生徒理解に努めているものの、生徒のことを真に理解しようとしていないことを気づかされました。生徒が授業や人との関わりの中で、特に何に困っているのか、周囲の教員や保護者と連携しながら、まずはきちんとアセスメントをしたいと思います。
・「気になる子供」と言っても、多種多様な見方や関わり方があることを改めて学ぶ機会となりました。何より、困り感を感じている生徒や保護者のために何ができるのか、できないことやダメなことを指摘して終わりではなく「次に何をするのかを考えること」が我々の仕事の大切な点であることを感じさせられました。
9月18日(木)標記講座を開催しました。15名の先生方が受講されました。
午前は、育てたい資質・能力を意識した指導の在り方をテーマに、実践につながるヒントを得られるよう、ペアで体験を通して様々な指導法に触れる時間としました。
午後は、拓殖大学の西村秀之教授を講師にお招きし、ご講義をいただきました。講義を通して、授業改善の視点を明確にするとともに、学習指導要領への理解を一層深めることができました。また、「理想の子供像」や「目指す教師像」を言語化する活動を通じて、受講者一人一人が授業改善の方向性を見い出すことができました。さらに、受講者同士の交流や体験の場も多く設定され、学びの多い充実した3時間となりました。
【講座の内容】
午前 講義・演習 中学校英語教育における指導技術の向上と授業改善へのアプローチ
青森県総合学校教育センター 指導主事 長谷川 紘一
午後 講義・演習 中学校英語教師に求められる授業改善
拓殖大学 外国語学部 英米語学科 教授 西村 秀之
【講座の様子】


受講者の感想】(一部抜粋)
・授業改善の視点が明確になり、とても有意義な時間となりました。ぜひまた受講したいです。
・1・2年生の題材でも、これほど多様な方法で指導できることに驚きました。復習や定着のために、3年生でも実践してみたいです。
・これまで自分が取り組んでいた音読や授業の導入が、いかに内容の薄いものであったかを再確認することができました。生徒のもつ能力を活性化させる授業の組み立てを、改めて考え直したいと強く感じました。
・自己紹介のアプローチ方法が、自己紹介にとどまらず、授業内容の推測や生徒が苦手とする疑問文作成などにも幅広く活用できそうだと感じました。
・これまで悩んでいた目的や場面・状況の設定の仕方、リスニングを聞きたいと思わせる工夫、音読の方法など、今まで取り組んだことのない指導法を学ぶことができました。
9月29日(月)文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官 平田朝一氏を講師として、「指導と評価の一体化を目指す美術の授業」についての講義と協議・演習を行いました。
【講座の内容】
講義「指導と評価の一体化を目指す美術の授業」
演習・協議「指導と評価の一体化を目指す美術の授業づくり」
【講座の様子】


【受講者の感想】
・午後の演習・協議で特に印象に残っているのは、「素材から主題を考える方法」「美術の授業と地域連携」についてです。テーマを与えられて制作するのはとても久しぶりで、生徒の気持ちも想像しながら制作することができました。同じテーマでも主題と実際の完成作品は全員異なっていて、視点の違いによる発想の豊かさを学ぶことができました。
・材料から発想を広げることの面白さを学びました。素材の良さや加工方法を実感的に学ぶことができ、自分の手で素材を動かすことで、アイデアが広がっていくきっかけにもなる、という体験をさせていただきました。自由に材料を選んだり試したりすることは、生徒にとって自己決定の機会にもなります。美術は、課題にぶつかることで解決させようと試行錯誤し自己決定を行うという、他の教科にはない良さがあるということを学び、まずは生徒が主体的に自己決定できるよう、支援できる教員でありたいと思いました。
9月24日(水)に標記講座が開催され、14名の受講者が「学習指導要領の趣旨を踏まえた授業づくりと家庭科における評価のポイント」をテーマに研修を行いました。講師の茨城大学 教育学部 教授 石島 恵美子 先生より、小・中・高の学習指導要領の比較、なぜ問題解決型学習が必要なのか、問題解決型調理実習の実践事例など、専門的な知識や、授業のヒントとなるような事例を聞くことができ、とても有意義な時間となりました。
【研修内容】
講義 学習指導計画作成における現状と課題の把握
講義 学習指導要領の趣旨を踏まえた授業づくりと家庭科における評価のポイントについて
(講師)茨城大学 教育学部
教授 石島 恵美子 氏
講義・演習 学習指導要領を踏まえた家庭科の学習指導計画
【講座の様子】
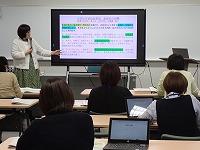

【受講者からの感想】
・石島先生の講義は、学習指導要領についてわかりやすく参考になりましたし、課題解決を取り入れた調理実習について、目から鱗が落ちる思いで、参考になりました。また、ポートフォリオの内容もとても参考になりました。時間が許せば、評価の部分についてもっと教えていただきたかったです。午後の授業デザインの作成では、班で行ったことで、普段難しいと考えていることも考えやすかったです。なかなか、勉強する機会がなかったので、とても良い機会になり、少しでも意識しながら普段の授業を改善していきたいと感じました。
・大変わかりやすく説明していただき、授業をイメージしながら講座を聞くことができました。特に、食分野については、これから取り組もうと思っていましたので大変参考になりました。今回教えていただいた要点等を確認しながら今後の授業作りに取り組んでいきたいと思います。学習指導計画について、なかなか作成できないまま授業に取り組んできていました。今回の講座を受講して、手探りながらもできそうな感じです。
・生徒に何を身につけてほしいのか、単元の目標を明確にしながらポイントを絞り、学びを深めるための工夫や声がけの必要性を確認できました。特に問題解決的な学習の取り組みでは、指導要領に課題発見のヒントが隠されており、生徒との対話的なやりとりの中から課題をもたせるためのしかけをどのように促していくかを考える機会となりました。
また、後半はグループごとに問題解決的な学習に取り組みましたが、とても学びがありました。同じ食生活と健康に関わる内容でも、何を課題とするか、またどういう視点から切り込んで展開し実践に繋げ、振り返りをさせていくのか、向かう目標は同じであっても展開やポイントとなる視点が異なっていてとても興味深かったです。
9月25日(木)、26日(金)に標記講座を開催しました。中学校の4名の先生が受講され、技術の見方・考え方を働かせた主体的・対話的で深い学びのある新しい授業づくりに向けて、計測・制御の情報コンテンツや双方向性のあるプログラミングの演習に取り組みました。
〔講座の内容〕
1「情報の技術」の指導内容と授業づくりについて
2 ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツの設計・制作
3 教材紹介や生成AIの授業活用について


(受講者の感想)
・情報分野の授業でのツールについてたくさん紹介頂きました。自らの研究や今後の学校現場での授業に生かしていけたらと思います。
・来年度、免許外で4年ぶりに技術を担当する可能性が高いため、すぐに使えそうな演習内容でよかったです。
・情報について,たくさん学べたので,目的は達成できました。次年度の希望としては,次期学習指導要領について,材料加工・生物育成・エネルギー変換が情報との複合を前提とするのであれば,そのような複合内容を扱う実習で(できればmicro:bitで)研修を受けたいです。
・次期学習指導要領の展望や生成AIなど,個人的に気になる内容を取り扱っていただいて大変勉強になりました。あらためて,「micro:bitを学ぶ」授業から脱却して,問題解決をする授業をしないとなあと考えさせられました。大変勉強になりました。ありがとうございます。
9月25日(木)~26日(金)の2日間、標記講座を開催し、20名の先生方が受講されました。国語科の「話すこと・聞くこと」「書くこと」領域において、付けたい力に応じた効果的な言語活動の在り方について学びました。受講者一人一人が新たな学びや気付きを得ることができ、今後の実践に生かしたいという前向きな感想が多く寄せられました。
【講座の内容】
1日目(9月25日)
午前:講義 「子供の成長に応じた言語活動の実践」
講義 「主体的・対話的で深い学びを実現する言語活動の実践」(校種別)
午後:演習 「主体的・対話的で深い学びを実現する言語活動のモデルづくり[話すこと・聞くこと]
2日目(9月26日)
午前:講義・演習 「新聞で育てる言語能力」
東奥日報社 販売局NIE・NIB推進部 専任局次長 三浦 博史
午後:演習 「主体的・対話的で深い学びを実現する言語活動のモデルづくり[書くこと](校種別)
【講座の様子】





【受講者からの感想】
・自分自身、国語が苦手で、どのような授業をすれば楽しく学ぶことが出来るのか悩んでいました。しかし、国語の力を身に付けるための言語活動が様々あること、そこから国語の力が身に付いていくことを学びました。
・「話すこと・聞くこと」「書くこと」の面白さを改めて実感しました。講座の様々な演習を通して、自分の頭で考えたことや周りの人が考えたことを交流して、また新たな考えが生まれていくことの面白さや楽しさを体感することができました。言語活動を工夫すると、こんなにもわくわくする授業になるんだなぁと思いました。私は、普段の授業の中で何となく指導してしまっているところがあったので、指導事項を明確にし、目的やねらいをもった活動をすることで、子供たちが生き生きと学べる授業を作っていきたいと思いました。
・学習者体験を通して、様々な言語活動を実際にやってみる時間が数多くあり、学習者目線で、考えることができたことが今後の授業を考えるうえでとても参考になりました。自分自身のこれまでの授業を振り返ってみると、「教科書を教える」ことがどちらかというと多かったような気がします。単元の学習を通して効果を上げるために、今あるものを使って、新しい活動に挑戦するために、「教科書で教える」ためのヒントや実戦例を数多く得ることができました。
・講座のなかで、青森県の子供たちは「情報を整理する力」が弱いという話がありました。確かに、現代は簡単に「情報を手に入れること」はできます。ただ、得た情報の中からどの情報が必要か自分で精査し、まとめることが苦手な生徒が多いと普段から感じています。これは、普段の授業でまとめる際に、教師がまとめてしまったり答えてほしい方向に導いてしまったりしているからであると自覚しています。今回の研修で、生徒自身が自ら課題意識をもち、その課題は自分にとってなぜ必要なのかを考えさせることが、これからの実生活や社会で求められると改めて学びました。
9月24日(水)、25日(木)の2日間、標記講座を開催しました。プログラミング教育と環境構築、ライブラリとWebAPIの活用、事象のモデル化とシミュレーションなどについて学びました。
【講座の内容】
・プログラミング教育と環境構築
・応用的プログラム
・ライブラリとWebAPIの活用
・事象のモデル化とシミュレーション
【講座の様子】
【受講者の感想】
・Pythonのプログラミングの基礎が学べました。来年度から生成AIとプログラミングの科目を受け持つことになるので、その授業のイメージが湧きました。大変参考になりました。
・Colabを使用した演習だったので、比較的簡単に生徒に授業することが体験できました。また、情報を担当している先生方と受講することで、情報交換をすることができました。わかりやすい講義ありがとうございました。
・専門外で大丈夫だろうかと不安でしたが、あっという間でした。知識より使ってみて駄目なら直してを生成AIを利用してできると知り、仕事でも活用してみたいと思いました。
9月17日(水)に標記研修講座を開催しました。
講師として東京学芸大学大学院教授の西村圭一氏、東京学芸大学准教授の藤村裕子
氏をお招きし、講義・演習をしていただきました。また、百石高等学校の木村育先生
をお招きし、実践発表をしていただきました。西村教授、藤村准教授による講義・演
習では、探究のプロセスを意識したワークショップ形式の構成となっており、受講者
の課題を設定した後、木村先生の実践発表を通して解決の方向性を見出すという、学
びと気付きの多い一日となりました。
■講義「探究的な学びの充実へ向けて」
(講師)県総合学校教育センター
指導主事 青木 雅俊
■講義・演習「学校教育における探究的な学びの実装化」
(講師)東京学芸大学大学院
教授 西村 圭一
■発表・協議「総合的な探究の時間の取組」
(発表者)県立百石高等学校
教諭 木村 育
(助言者)東京学芸大学
准教授 藤村 祐子
【受講者の感想】
・あっという間でした。ちょうどよいボリュームのインプットと、これでもかというく
らいのアウトプット。私にとって、これまでのことを振り返ることのできる時間とな
りました。そして、提示していただいた研修プログラムを、授業づくりにも生かして
いきたいと思います。
・今後校内の中で探究活動をけん引していく立場になっていくと思うので、その際の研
修の手法などを今後も学んでいきたいです。総探に関する研修にはいろいろ参加して
きましたが、答えや事例を求めるのではなく、他校の事例から自分の学校の探究活動
を改めて価値づけ見つめ直しながら今後の方向性を見いだしていくことが大切だと気
付いたので、次年度も是非ともお願いしたいです。
・今回の研修講座はとても充実したものでした。内容が濃かった分、何回も反芻しなが
ら、少しずつ自分の学校の実情に合わせて取り組んでいきたいと思います。次回もこ
のような形式の研修を希望します。
・総探へのイメージが自分自身の中でむずかしいものから、やってみようという気持ち
になった。本校は地域や外部との連携がとても多いため、それを強みとしてその中で
どのような探究活動を促していくかを同僚と対話をしながら進めて行きたいと思った。
9月12日(金)に高等学校における特別支援教育研修講座が開催されました。受講者は13名で、特別な教育的ニーズがある生徒の支援について理解を深められた様子でした。
【研修内容】
1 講義「小・中学校における特別支援教育」
2 発表「高等学校における特別支援教育」
発表者 県立六ヶ所高等学校 教諭 太田 美千之
3 演習・協議「個に応じた支援のさらなる充実に向けて~より効果的な個別の指導計画の作成~」


【受講者の感想】
・高校にも一定数特別支援が必要な生徒がいることを再確認することができた。小・中学校での指導内容を確認できて良かった。
・生徒のとった行動の背景にある理由や目的を正しく理解することの大切さがよく分かった。日々の実践でぜひ生かしたい。
・六ヶ所高校さんの発表で、生徒がとても楽しそうに活動している様子が伺えて、普段の学校生活が充実していることが分かった。他校に視察に行ったり研修に参加したりして、それを校内研修で情報共有をする。先生方一丸となって「授業のUD化」に取り組む。チーム六高の意識の高さが伝わってきた。私も他の先生方と協力して、生徒のために尽力していきたい。
・指導計画の作成はよく分からずハードルの高いものと敬遠しがちだったが、手順を追った演習でその意味や内容を理解することができた。今後経験を積んで生徒にとってよりよい指導計画の作成に取り組んでいきたいと思った。
・支援が必要な生徒への対応に手詰まり感を感じていたが、グループの先生方と協議してみてまだまだできることがあると気づいた。校内でも日常的に生徒についてミニ協議をしていきたい。
9月5日(金)、標記講座を開催しました。参加者は小学校7名、中学校7名、高校4名、特別支援学校2名の合計20名でした。
「新しい時代に問われる養護教諭の専門性について」と題し、愛知教育大学 名誉教授 後藤 ひとみ先生から、養護教諭という職の発展の歴史や養護教諭を取り巻く昨今の情勢、これからの時代に求められる養護教諭の役割について、これまでの豊かなご経験から、わかりやすく教えていただきました。後半は、「養護教諭の倫理綱領」をもとに日々の仕事を振り返り、その専門性について考える機会になりました。また、養護教諭の専門性をいかした支援と連携の在り方やいつの時代にあっても変わらない養護教諭の役割について、グループワークを通して、さらに学びを深めることができました。後藤先生からは、「養護教諭」としてこれからも学び続けるための勇気と元気をたくさんいただきました。
【研修内容】
講義・演習「新しい時代に問われる養護教諭の専門性について」
愛知教育大学 名誉教授 後藤 ひとみ 氏
【講座の様子】
【受講者の感想】
・後藤ひとみ先生からパワーをいただきました。養護教諭は土台でもなく黒子でもなくコーディネーターであること、一人一人の幸福を願って対応すること、子どもの状態によって健康管理と健康教育の割合を考えることなど、心にストンと落ちてきました。最後のジレンマワークを通して、養護教諭の臨機応変さの必要性を強く感じ、いつでも「今、優先することは何か、今できることは何か」を考えながら過ごしていきたいと思いました。貴重なお話を伺うことができました。ありがとうございました。
・後藤先生からの貴重なお話を聞いて、養護教諭の専門性やあり方について考えたり、養護教諭としての自分自身を振り返ることができ、大変良い機会となりました。後藤先生の「大切なのは子ども。そのために何をすべきかを念頭に置く」「子どもを支えるためにまずは自分自身が健康で幸せであること」という言葉が印象に残りました。
・養護教諭とは何か、核となるのはどのようなところか、など様々な点から養護教諭について改めて考えさせられる場となりました。これから先、子どもたちのために何ができるのか、そのために必要なことは何かを日々考え続け、教員と情報共有をしたり研修に参加したりして、時代に合わせた知識と技術のアップデートもし続けていきたいと思います。また、養護教諭としての職の専門性や対応の根拠をしっかりもち、子どもたちへ責任ある言動をし続けていける養護教諭でありたいと強く感じました。
9月5日(金)標記の講座を開催しました。小学校から7名の受講者が参加し、日頃の授業実践を振り返ったり、器械運動系の特性を生かした授業づくりについて学んだりしました。受講者一人一人が新たな学びや気付きを得ることができ、今後の実践に生かしたいという前向きな感想が多く寄せられました。
【講座の内容】
午前:協議「体育科の授業実践を振り返って」
:講義・協議「良質な体育科の授業実践を目指して」
講師 青森県総合学校教育センター 指導主事 石田 真大
午後:講義・実技「器械運動系の特性を生かした授業づくり」
講師 宮城教育大学 教授 木下 英俊
【受講者の感想】
・同じ悩みをもつ先生方と話し合うことで、自分の悩みがさらにはっきりしたり、解決方法の糸口が見えたりしました。一つのテーマで意見を出し合ったり考えたりするのは研修でしか機会がないので、大変貴重な時間でした。
・うさぎ跳びやゆりかごにも段階があり、目指す動きに応じて、その段階を使い分けていくことが必要だと学びました。特に、マット運動が苦手な子供に対して、スモールステップで教えていきたいと思います。
・なんとなくこうすればできるという曖昧な捉えが、はっきりとした捉えに変わるような、非常に腑に落ちる講義・実技でした。特に実技では、自分自身が体の使い方を考えて実践することで、より子供たちに教えやすくなったと思います。場の設定などを工夫することで、誰でも参加できる授業を目指していきたいです。
9月8日(月)に標記講座を開催し、幼・小・特合わせて19名の先生方が参加されました。
ものづくりを中心とした演習を通して、生活科授業の在り方について学びました。
午前は、新谷祐貴先生をお招きして、ものづくりの具体的な教材を紹介していただきながら、気付きの質を高めるための考え方を中心に講義・演習を行いました。
午後は、ものづくりの授業場面を想定して、実際にものづくりの内容を考えて体験する演習をし、深い学びに導くためにどのように働きかけていくかを協議をしました。
講義・演習・協議を通して、児童の体験と表現の相互作用を重視した「見取り、働きかけ」から深い学びへと導くためにどう授業を改善していくかについて、たくさんの気付きを得た研修となりました。
【講座の内容】
講義・演習「気付きの質を高める生活科の授業づくり」
(講師)千葉大学教育学部附属小学校 専任教員 新谷 祐貴 氏
講義・演習「身近な素材を通した指導と評価の在り方」
(講師)県総合学校教育センター 指導主事 山口 繁弥
【受講者からの感想】
・実技講座が充実していて、わかりやすかったです。低学年でも簡単にできそうな教材がたくさんありましたし、実際に先生がどのような場面で取り入れているのかもお話ししてくださったので、まずはその場面で実践してみたいと思います。
・児童の気付きに対して、さらにその気付きが深まるように、教師も意図的に言葉がけをしなければいけないのだということがとても勉強になりました。
・同じ班の先生方とおもちゃ作りをすることで、児童がつまずきそうなところを考えたり、気付かせるためにどのような支援をすればよいかを考えたりすることができました。やはり子供たちに気付かせるための声がけはとても大切だと実感できました。
・特別支援教育には生活科はありませんが、興味関心をひく教材は必要不可欠であり、一人一人の興味関心のある教材を使っての学習に日々取り組んでいます。今回の研修は、特別支援教育の現場でもたくさん活用できると感じました。また、子供のつぶやきがとても大切で、その「気付き」を見逃さないように、深い学びにつなげていきたいと思いました。
令和7年9月18日(木)に、文教大学教授の会沢信彦氏をお招きして、「今日から始める教育相談研修講座」を開催いたしました。
生徒指導はガイダンスとカウンセリングの訳語であること、教育相談が学級経営・授業のベースになっていること、多面的に生徒を捉え分けて考えることでアセスメントがより手軽にできること、認知やトラウマについての事例紹介、教育相談・カウンセリングについて学べる書籍や機会紹介など、幅広いテーマ・目標についてお話いただきました。
他校種とのグループ交流を設けていただくだけでなく、講義終わりに数多く出された質問へも丁寧に応答くださり、教育相談についてより学びたくなる貴重な機会になりました。
【研修内容】
講義・演習「教育相談の理論と実践」
(講師)文教大学 教授 会沢 信彦 氏
【講座・演習の様子】

【受講者からの感想】
・講義の質問にデジタルキャンバスを使って自由に投稿できるようにしたことは非常に有効だと感じた。大勢いる中で挙手して質問するよりも、ずっとハードルが低い。学校でも導入を検討してみたい。
・生徒指導と教育相談は別物として考えていましたが、会沢先生からイコールだと教わりびっくりました。
・教育相談には生徒を支えるという意味も込められ、何か問題があったときには、なぜそのようなことになったのかの背景を考えたり、わかろうとしたりすることで自分の気持ちも楽になり、相手に伝えることでわかってもらえると生徒も感じ安心するのかと思います。
・今所属している学年では、希望する学年所属の先生ならだれとでもできるシステムをとり、迅速に共通理解を図るようにしています。
・今回の講座内容を伝達して、生徒の困り感や実態に合わせた支援をしていきたいと思います。
・現在の勤務校では、生徒指導と教育相談が切り離されている部分と、連携できている部分があり、組織として整備されていない面もあると感じた。このような学びの機会を自身で作り、少しでも学校に貢献できるようにしたい。
9月10日(水)、今日から始める不登校対策研修講座が開催されました。受講者は小学校2名、中学校14名、高等学校7名、特別支援学校6名、聴講者7名、合計36名でした。不登校の予防に重要とされるリレーションを作る方法や、久しぶりに登校した生徒に声掛けをすることを想定した演習、不登校の生徒へ働きかける上でどのような工夫ができるかについての意見交換等、非常に実践的な内容を学ぶことができました。
【研修内容】
講義・演習「不登校児童生徒の理解とその対応」
(講師)明治大学 教授 諸富 祥彦 氏

【受講者の感想から】
・不登校の初期、中期、後期における対応についてすぐに実践できる方法をたくさん教わり、日々の実践に生かしたいと思いました。また、不登校の予防に向けた方策については、教師の精神状態や働く姿勢が大きくかかわることを学んだので、「笑顔、フットワーク、声掛け」の3つを心がけたいと思いました。
・リレーション、援助希求力の重要性を学ぶことができました。また、生徒にとっての安心安全な学校(学級)を構築するために、ルールが守られることが大切であるということを再認識することができました。
・「不登校の子の体は砂袋のように重い」という認識を持つこともとても重要だと感じました。欠課時数のことよりも、まずは本人の心や体とどのように向き合っていけばよいのかを重視して接していくべきだとわかりました。
・不登校の生徒ととの面談(会話)の仕方であったり、家庭訪問の時期や訪問する先生の人選など、不登校の生徒に対して、様々な方法があることを知ることができました。
9月10日(水)に標記講座を開催しました。小学校や特別支援学校の先生方が受講され、プログラミングの授業づくりについて楽しく学びました。
【講座の内容】
1.講義「小学校段階におけるプログラミング教育の在り方」
講師 弘前大学 教授 上之園 哲也先生
2.演習「プログラミングツールの演習」
【講座の様子】


【受講者アンケートより】
・プログラミング教育のあり方やこの先の位置付けについて理解でき、自分の目標は達成されたと感じます。
・3年目ですが、目から鱗の内容でした。来年も受講したいです。
・大学入試での「情報I」でプログラミング教育が関係すると聞いたことがあったので、小学校も今のままではダメだと思っています。しかし、プログラミングは専門的なのでなかなか子どもたちに指導するのも難しいです。でも、2年間この講義を受けているので、今年はプログラミングもやりたいと思っています。今回の講義を聞いて、参観日に親子でプログラミングをやりたいなと思いました。
・ポケモンのゲームでプログラムをつくることを通して、操作や処理のしかた、「プログラミング的思考」について学び、考えることができました。
・本校の特性を考えると、日常生活における順番の理解、アンプラグドプログラミングによる実際に体や手を動かして体験する段階から踏んでいく必要があると感じた。思考の整理、複雑な問題の分解などの思考過程を身につける、学習するには自立活動などで効果的に扱えるのではないかと思った。
・ポケモンを使ったスクラッチを初めて使い楽しく演習できた。ぜひ子供たちに使わせたい。
・充実した時間、学びをありがとうございました。
9月11日、12日に標記講座を開催しました。
1日目は、問いを大切にした授業づくりやICTの効果的な活用について講義・演習を行いました。
2日目は、大妻女子大学澤井陽介教授をお招きし、午前は「主体的・対話的で深い学びの実現を目指す問題解決的な学習の在り方」と題してご講義いただき、午後は単元作りの演習を行いました。子供たちの「問い」を大切にした授業改善について学びました。
【講座の内容】
1日目 講義・演習
「主体的・対話的で深い学びの実現を目指す問題解決的な学習の授業改善」
「ICTの効果的な活用」
講師 県総合学校教育センター 指導主事 津嶋 由香
実践発表「思考力・判断力・表現力等を育てる社会科教育の実践」
発表者 野辺地町立野辺地小学校 教諭 加賀 千裕
2日目 講義・演習
「主体的・対話的で深い学びの実現を目指す問題解決的な学習の在り方」
講師 大妻女子大学 教授 澤井 陽介 氏
【受講者からの感想】
・問題解決的な単元を通した授業デザインのポイントについて、学習問題の設定の仕方や、ICTの効果的な活用方法
など体験することができ、新しい気付きが多くありました。
・講義を受けて、今回2つの単元について考えることができたので、すぐに社会の授業で活用します。また、地図を使っ
たICTの活用もとても面白かったので、社会科だけではなく総合などとも関連させて子供たちにも使用させたいと思
いました。
・講座を受講して、社会的事象をいかに児童にとって身近にするか、疑問をもたせ、予想を立てさせ、調べたいと思わせ
るかが大切だとわかりました。
9月11日(木),12日(金)に標記講座が開催され,県内の中学校,特別支援学校から12名の先生方が受講しました。
【講座の内容】
○1日目
1.講義「思考力、判断力、表現力等の育成を図る社会科の授業づくり」
2.講義・演習「ICTを活用した社会科の授業」
3.発表「思考力、判断力、表現力等の育成を図る社会科の授業実践」
大鰐町立大鰐中学校 教諭 三上 明日紀
4.演習・協議「ICTを活用した社会科の授業づくり」
○2日目
1.講義・演習「主体的・対話的で深い学びの実現を目指す問題解決的な学習の在り方」
大妻女子大学 教授 澤井 陽介
【講座の様子】




【受講者の感想】
・個別最適な学びや協働的な学びが、「主体的・対話的で深い学び」を実現するためのものであるということを忘れてはならないと感じました。
・単元のまとまりを大切にした授業づくりについて、また、生徒がこれからの社会を生きていく際に必要な力を育むために考え続けていこうと改めて思いました。
・単元について助言をいただきながら演習するのはもちろんですが、先生方と一つの単元(本時)について考え、作る機会はなかなかないので、とても良い時間になりました。
9月17日(水)標記講座を開催しました。聴講の先生方を含め12名が参加しました。午前中に、Gemini等のツールを活用しながら、導き出された答えからそれぞれの考察や行動判断にどのように結び付けていくのかを学び、午後は社会人基礎力をベースとしたルーブリック評価表の作成の演習を通して、思考の可視化やグラデーションの難しさを実感しました。変化の激しい情報化社会の中において、ご自身の教科でどのような人材を育成していくのかについてじっくりと考え、共有しあう大変有意義な時間となりました。
【講座内容】
「DX時代に求められる産業教育のあり方」 ~生成AIの可能性をふまえて~
講師 城西大学 副学長 栗田 るみ子 氏
【講座の様子】


【受講者の感想】
・ルーブリックを示すことで生徒に達成度を示すことができると考えられ、次年度の取り組みに組み込めそうだと思いました。民間企業の視察や生成AIの活用方法など幅広く学ぶ機会が得られました。
・本講座の目標である生成AIをはじめとするIT技術とのかかわり方を中心に必要とされる、知識・技術を学ぶことができたと考えます。生成AIで、調べ物をすることしか活用方法を理解していませんでしたが、栗田先生のおっしゃるように使い方次第では私たちの仕事を減らし、その分別のことに時間を注げると感じました。現場に戻りましたら、積極的に活用していこうと思います。
・生成AIを有効活用できれば、授業のやり方も変わるだろうし、業務の効率化にもつながり、生徒と直接かかわる時間が増えるので、それが理想です。技術を身に付けながら、並行して業務改善に取り組みたいです。
9月2日(火)、標記講座を開催しました。小・高・特別支援学校の9名の先生方が受講、そして特別支援学校の1名の先生が聴講され、Googleドライブ、Google Forms、Google Classroomなどの操作方法について学びました。また、生成AI(Gemini)の操作方法を体験して頂きました。
【講座の内容】
Googleドライブの機能と基本操作
Googleアプリの機能と基本操作
GoogleClassroomの活用
【講座の様子】


【受講者の感想】
・Google Workspaceの基本的な操作から、応用編まで幅広く勉強することができてよかったです。特に、提案モードの機能のよさを生かすことで、課題の添削が容易にできるところが、初めて知る機能だったのでとても印象に残りました。また、詳細な設定方法について知ることができ、とてもよい機会となりました。
・学校で起こった不具合やインシデントも設定の部分に起因することが多いため、共有の設定については確認が必要だと感じました。学校に持ち帰り、講座内容を先生方へ周知したいと思います。
・Google Formsの基本的操作方法・作成について、よく学ばさせていただきました。早々に作成したいアンケートフォームがありましたので、学校に戻りましたら作成していきたいと思います。
・基本的な使い方を学ぶことができたので、受講目的は達成できたと思います。所属校に持ち帰ってミニ研修会を行う予定なので、もう少し自分でも操作に慣れるように頑張りたいです。
9月2日(火)標記講座を開催しました。小学校と特別支援学校の33名の先生方が受講され、「言語活動の充実」の考え方で、日々の授業においてベースとなる考え方や様々な手法について、また、それらを通して「子供主体の国語授業への転換」について学びました。
【講座の内容】
・講義・演習「国語授業の「個別最適な学び」と「協働的な学び」」
(講師)京都女子大学 水戸部 修治 教授
・講義・演習「主体的・対話的で深い学びの授業改善とICT」
(講師)県総合学校教育センター 指導主事 齋藤 紀行
・講義・演習「資質・能力の育成を目指した単元構想」
(講師)県総合学校教育センター 指導主事 齋藤 紀行

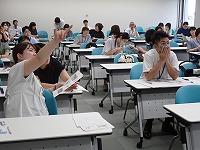


【受講者の感想】
・本講義・演習では、これまでの経験でようやく形になってきたと感じていた国語の授業像が良い意味で壊されました。私はこれまで水戸部教授がおっしゃっていた「昭和の授業」をやっていたと思います。明日からでも「令和の授業」に変えるためにも、指導事項を踏まえた魅力的な言語活動の設定をして取り組んでいきたいです。
・講義・演習の中で紹介された授業実践は、どれも指導事項にあったつぶやき・質問・発言が子供から出てくるものでした。その環境をつくるための手立てとして、学習計画表や活動したくなるめあての設定、交流の場の設定、モデル動画の活用、マトリクス表の活用など様々な工夫がありました。「子供がどう学ぶか」「必然性はあるか」「指導事項にあった活動か」など考えながら、これから授業していきたいです。
・実際に指導計画を作成したことで、ゴールを明確にした指導計画をどのように作成すれば良いかイメージが湧きました。日々の授業を考える際にも、ゴールから逆算して考える授業づくりは、有効に活用できそうだと思いました。
・教えていただいたことは、他教科にもつながると感じました。他教科を指導する場面でも活用していきたいです。