




8月31日(火)、9月1日(水)の2日間、13名の先生方が研修に臨みました。
今年度は、2日間とも非集合による開催となり、GoogleMeetによるオンライン研修を行いました。
1日目は、「話すこと・聞くこと」領域に焦点を当てて、学習指導要領に沿って、話す・聞く力を育成する授業づくりに向けて、付けたい資質・能力を明確にした授業改善について理解を深めました。
2日目は、「GoogleClassroom」と「ロイロノート」を使用して、タブレット端末を活用した国語科の授業について、学習者体験をして実践への意欲を高めました。

オンラインによる研修が初めての方が多かったのですが、2日間、大きな接続トラブルもなく無事に研修を行うことができました。
受講者の皆さんは、多くのエッセンスを得て、明日からの実践へとつなげることができました。
【受講者の感想】
・言語活動を充実させるための方法をたくさん学ぶことができました。ちょっとしたアイディアや工夫で,言葉は広がり深くなっていくので,今回の講座で学んだことを,子どもの実態に合わせながら生かし指導していきます。
・オンラインでの実施ということでしたが、リモート授業をするとこういう感じになるんだなというイメージをもつことができ、よい機会だったと思います。機器の操作に関しては、国語の授業だけでなく、他の教科にも生かせる内容でとても勉強になりました。
・GoogleWorkspaceは使ったことがなかったので,ロイロノートにはない機能が色々あるのだなと勉強になりました。また,ロイロノートにも自分がまだ活用したことのない機能があったので,授業の中で活用してみたいと思いました。
8月31日(火)C19 学びを実感させる高等学校理科研修講座[物理]が開催されました。
この講座は、「授業において観察・実験をどのように取り入れるか」という視点と、「どのような資質・能力を身に付けるために観察・実験を取り入れるのか」という二つの視点に立ち、先生方の授業力の向上をねらいとして、毎年開催しております。
今年度は、急遽、オンライン開催となりましたが、「理科の見方・考え方を働かせる授業デザイン~観察・実験やICTの活用を通して~」では、Google Workspace を使っての演習を行うことができました。非集合形式だからこそ、可能性を感じることのできる内容となりました。また、「身近な素材を用いた観察・実験とその教材開発」では、各単元での実験動画を紹介しながら、計算や、授業との関連性の持たせ方についての協議を行いました。

・演示実験や実験動画を授業に取り入れ、生徒の理解度を高めたい。
・実験・観察は数式にイメージを付与するために大切なものだということが、今日の講義で痛感できました。
・ICTを利用した授業にしても、実験を取り入れた授業にしても、現状に満足せずに色々試していかなくてはいけないと強く感じました。














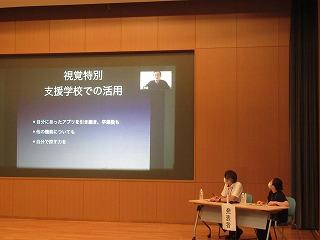













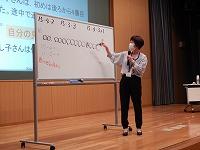
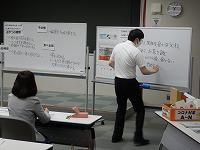



8月18日(水)、「今日から始めるグループ・アプローチ研修講座」を開催しました。講師である聖徳大学鈴木由美教授は、新型コロナウイルス感染防止のため、オンラインによる講座形式となりました。
集団内でのより良い関係づくりを目指すグループ・アプローチの講義・演習を通して、子供同士のコミュニケーション能力向上のため、教師自身が児童生徒の視点に立って研修に取り組みました。
タブレットを活用したグループ・アプローチにも挑戦しました。事前準備や操作性など、まだ課題もありますが、今後の可能性を感じることができる内容でした。



【受講者の感想】
・ラッキー7や間違い探し等の対人関係ゲームを実際に行い、参加者との距離が近くなったことを肌で感じました。どちらも準備も簡単なので、早速実践したいと感じた。
・集団における自らの存在意義、自己を肯定的に捉えるために、湖南会の演習で取り組んだゲームや手法はとても効果的であると感じた。
・グループ・アプローチ集に載っている対人ゲームを実際にやって、研修参加者と懇談する機会が欲しいと思った。経験者の成功談や失敗談を聞きたかった。
・コロナ禍において、グループ・アプローチは実践しにくいと感じていましたが、タブレットを活用したやり方をお聞きし、時代の進化に驚いた。
・口頭で発表が困難な子供にも、書いた内容をタブレット経由することで他の人にリアルタイムで瞬時に伝えるなど、活用方法を模索してみたいと思った。


